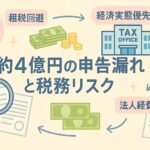「常照我」の直訳:
「(阿弥陀如来が)絶え間なく私を照らし護ってくださる」
「常照我」(じょうしょうが)は、浄土真宗の『正信偈』に登場する仏教用語である。その直訳は「(阿弥陀如来が)絶え間なく私を照らし護ってくださる」という意味を持つ 。語句は「常」(絶え間なく、いつでも、どこでも)、「照」(照らす、守る、導く阿弥陀如来の智慧と慈悲)、「我」(信心を持つ者全体)で構成される 。これは、阿弥陀如来の光明が衆生を常に包み込み、導く普遍的な働きを示す重要な概念である。
1. 語句の構成と基本的意味
- 常(じょう):
「絶え間なく」「いつでも」「どこでも」を意味し、時間的・空間的な継続性を強調します。 - 照(しょう):
「照らす」「守る」「導く」を表し、阿弥陀如来の光明(智慧と慈悲)が衆生を包み込むはたらきを指します。 - 我(が):
「私」という個人を指すが、ここでは「信心を持つ者」全体を包括的に示します。
2. 宗教的・思想的背景
この語は、源信僧都の『往生要集』にある「大悲無倦常照我身」(だいひむけんじょうしょうがしん)に由来し、親鸞聖人が『正信偈』で「大悲無倦常照我」と引用しました。核心的な解釈は以下の通りです:
- 大悲無倦(だいひむけん):
阿弥陀如来の「大いなる慈悲」は、衆生の煩悩や背きにも「倦(あ)きることなく」、見捨てることはない。 - 衆生の現実:
人間は煩悩に覆われて仏の光明を「見えない」が、それでも光明は確かに注がれている(例:『煩悩障眼雖不見』)。 - 摂取不捨(せっしゅふしゃ):
親鸞は「常照我」を「無碍の光明が信心の人を常に照らす」と解説。阿弥陀如来の光明は、衆生が気づかなくても「逃げる者を追いかけて摂め取る」という能動的救済を意味します。
象徴的な比喩:
- 親が子を見守るように、たとえ子が背を向けても見守り続ける阿弥陀の慈悲。
- 雲に隠れた太陽の光のように、煩悩に覆われても確かに存在する仏の護り。
3. 現代的意義:信仰者の実感として
- 主体的な信心:
「我(が)」を「信心の人」と限定したのは、仏光の普遍性の中でも「念仏する者」がその慈愛を「自覚する」ためである。 - 慰めと励まし:
困難や孤独の中で「常に照らされている」と気づくことで、生きる力が与えられる(例:『大安慰』の概念)。 - 平等性の強調:
「善人も悪人も」区別なく照らす光こそが、浄土真宗の「他力本願」の核心です。
4. 解釈のまとめ表
以下に主要な解釈ポイントを整理します:概念意味典拠常(じょう) 絶え間ない継続性 照(しょう) 光明による護り・導き 我(が) 信心を持つ者 大悲無倦 見捨てない慈悲 摂取不捨 逃げる者をも摂め取る救済
結論
「常照我」は、煩悩にまみれた人間を見捨てず、絶えず光明で包み続ける阿弥陀如来の慈悲を象徴する言葉です。親鸞聖人は、この一節を通じて「自力では救われない者が、仏の本願力によって護られる」という浄土真宗の根本思想を表現しました。現代においても、不安や孤独の中にある人々への「精神的支柱」として深く受け継がれています。
参考
大悲無倦常照我 - ことば こころのはな
(続きもの…最終回です)阿弥陀如来の救いとは…既にその救いの中にいる私たち。...
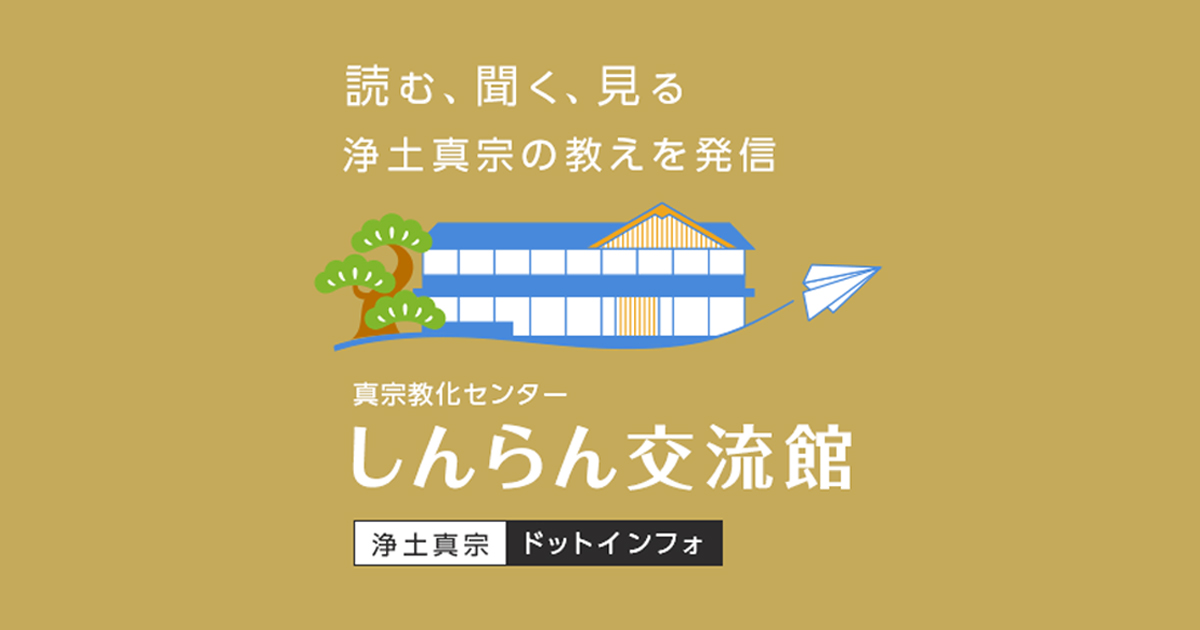
しんらん交流館HP 浄土真宗ドットインフォ | 真宗大谷派による浄土真宗のポータルサイト
真宗大谷派(東本願寺)が運営するしんらん交流館ホームページ(浄土真宗ドットインフォ)では、浄土真宗の教えにふれる情報、お寺のサポート情報、しんらん交流館で行われる行事などをご紹介いたします。