宇宙商業化の勢いは増しており、未開拓の空間には無限のビジネスチャンスが広がっています。多くの企業や投資家がこの分野に殺到しており、その様子は19世紀のゴールドラッシュに似ています。
ポイント1:なぜIT企業の巨人は宇宙を目指すのか
- 宇宙開発はもともと各国政府機関が主導していましたが、2005年のアメリカ政府の政策変更により商業化の流れが始まりました。スペースシャトル後継機の開発が民間に委ねられ、政府は民間から打ち上げサービスを購入するようになりました。
- 2010年にはオバマ大統領が新国家宇宙政策を打ち出し、民間企業の技術やサービスの活用、宇宙技術やインフラの商業利用などが推進されました。
- 宇宙ビジネスの世界市場規模は、2005年の約27兆円から2019年には約40兆8千億円に成長しており、このペースで進めば2040年代には100兆円以上になると言われています。これに伴い、宇宙関連ベンチャーへの投資も急速に拡大しています。
- 宇宙ビジネスの対象エリアは、静止軌道、低軌道、深宇宙の3つに分類されます。静止軌道では気象衛星や通信衛星などが商業化に成功しており、低軌道では小型衛星による精密な気象観測や宇宙旅行などが進んでいます。深宇宙では、月や火星の資源開発、有人宇宙飛行などが目指されています。
- 過去15年間でIT企業などが宇宙開発に参入し、投資を呼び込み、地上でのビジネス拡大につながっています。官公庁の宇宙予算は全体の25%未満となり、民間のサービスやプロダクトが大きく伸びています。この拡大の勢いは、19世紀のアメリカのゴールドラッシュに似ていると述べられています。
① 政策転換と市場拡大
- NASAから民間へ:2005年、米国政府がスペースシャトルの後継機開発を民間委託し、NASAは「顧客」として民間企業からサービスを購入する方針に転換。2010年のオバマ政権「新国家宇宙政策」で官民連携が加速。
- 市場規模の急拡大:2005年の17兆円から2016年には33兆円へ倍増。公的部門のシェアは25%未満に低下し、民間主導の成長が顕著。
② 3大宇宙エリアの特徴
- 静止軌道(高度36,000km):気象・通信衛星が中心で既に商業化済み。衛星延命サービスが新たなビジネスとして注目。
- 低軌道(高度100~2,000km):小型衛星のコンステレーション(衛星群)による地球観測や宇宙旅行が急成長。スペースXの「スターリンク」計画(全地球インターネット網)が象徴的。
- 深宇宙:月・火星開発や小惑星資源採掘が焦点。イーロン・マスクの「火星移住計画」やUAEの「火星ミニシティ構想」が具体化。
ポイント2:宇宙ビジネスを牽引するITの巨人たち
スペースX
イーロン・マスクが2002年に設立し、ロケット製造で後発ながら商業衛星の打ち上げサービス市場で躍進しています。ファルコンシリーズや世界最大のロケットであるファルコンヘビーを開発し、50回以上の打ち上げ実績があり、NASAの国際宇宙ステーションへの補給サービスも担っています。徹底的なコストダウンを実現しており、ロケットの再利用によりさらなるコスト削減が予定されています。アジャイル開発などのIT業界の手法を取り入れ、製造を効率化しています。
- ロケットの価格破壊:再利用可能な「ファルコン9」で打ち上げコストを60億円に圧縮(従来の1/3)。NASAのISS補給ミッションも受託。
- 長期ビジョン:火星移住を目指し、2022年時点で50回以上の打ち上げ実績。衛星インターネット網「スターリンク」で通信革命を推進。
ブルーオリジン
アマゾンの創業者ジェフ・ベゾスが2000年に設立しました。将来の宇宙経済圏を見据え、安価で安全なロケット開発に取り組んでいます。宇宙旅行が可能なサブオービタルロケットや大型ロケットを開発しており、垂直離着陸型のサブオービタル宇宙船「ニューシェパード」は高度100キロを超える宇宙空間への到達に成功しています。ベゾスはブルーオリジンに年間1000億円の投資を行っています。
- サブオービタル機「ニュー・シェパード」:垂直離着陸型機で4分間の無重力体験を提供。月面輸送機「ブルームーン」開発も進行中。
- 年間1,000億円投資:日本の宇宙予算(約3,000億円)の1/3規模を投じ、宇宙経済圏の創出を目指す。
Google(グーグル)
地球観測、通信、宇宙資源など幅広い分野に投資しています。2014年には小型衛星ベンチャーのスカイボックスを500億円で買収し、イーロン・マスクのスペースXが計画するブロードバンド事業にも1000億円以上を出資しています。
Meta(メタ)
17億人を超えるアクティブユーザーを抱え、インターネットインフラの普及を目指し宇宙ビジネスに参入しています。低軌道小型衛星によるグローバルなネットワーク構築を目指しており、周波数の割り当てなども課題となっています。ドローンなども組み合わせたマルチプルな運用を構想しています。
ポイント3:地球のビッグデータが産業を変える
- IT関連技術に多くの資金が流れているのは、宇宙をインターネットの延長として捉えているからです。宇宙にネットワークを構築することで、地球のビッグデータが入手でき、様々なビジネスが生まれると期待されています。
- 例えば、高性能な小型衛星による地球観測で、より精度の高い天気予報が可能になり、農業、畜産業、漁業の効率化・精密化が期待されます。作物の生育状況や品質を把握し、必要な場所への肥料散布など、より効率的な農業が可能になります。
- 宇宙データは金融、保険、健康産業などの生産管理も変革すると期待されています。
- 宇宙開発の長期的な目的の一つとして、人口増加や資源枯渇などの地球規模の危機に備え、人類が複数の惑星に住めるようにすることが挙げられています。特に火星が居住に適した惑星として注目されており、スペースXのイーロン・マスクは火星への移住計画を発表しています。今後十数年以内に地球と火星間で数千人を輸送する事業を開始し、40年から100年後には火星を100万人が居住できる地にするという壮大なビジョンを描いています。火星への輸送期間の短縮やチケットの値下げも計画されています。
① データ駆動型社会の到来
- 地球ビッグデータの活用:衛星画像×AIで農業の収量予測、漁業の魚群探知、災害監視などを高度化。自動運転車の位置精度向上にも貢献。
- 宇宙製造革命:無重力環境での3Dプリンティングや新素材開発が医療・電子機器産業を変革。
② 新たな経済圏の創出
- 宇宙旅行市場:サブオービタル旅行が100分の1のコストで実現。2023年時点で1,000人以上の予約が存在。
- 月面・火星ビジネス:月の水資源採掘や火星移住計画が進行。月面市場規模は2030年までに3,000億円に達すると予測。
③ 日本の挑戦と課題
- ベンチャー企業の台頭:インターステラテクノロジズ(ロケット量産)、アストロスケール(宇宙デブリ除去)などが国際競争に参戦。
- 官民連携の遅れ:米国に比べ投資規模が小さく、法整備やリスクマネーの不足が指摘される。
著者について
大貫美鈴(おおぬき・みすず)
宇宙ビジネスコンサルタント/スペースアクセス株式会社 代表取締役
日本女子大学卒業後、清水建設株式会社の宇宙開発室で企画・調査・広報を担当。世界数十か国から参加者が集まる宇宙専門の大学院大学「国際宇宙大学」の事務局スタッフを務める。その後、宇宙航空開発研究機構(JAXA)での勤務を経て独立。現在は、宇宙ビジネスコンサルタントとして、アメリカやヨーロッパの宇宙企業のプロジェクトに参画するなど、国内外の商業宇宙開発の推進に取り組む。清水建設の宇宙ホテル構想提案以降、身近な宇宙を広めるためのプロジェクトへの参画はライフワークになっている。アメリカの宇宙企業100社以上が所属する「スペースフロンティアファンデーション」の、アジアリエゾン(大使)としても名を連ねる。新聞や雑誌、ネットでの取材多数。
経済産業省国立研究開発法人審議会 臨時委員
国際宇宙航行連盟 米国連邦航空局 商業宇宙飛行安全委員会 委員
国際宇宙航行連盟 起業・投資委員会 委員
国際宇宙安全推進協会 サブオービタル宇宙飛行安全委員会 委員
国際宇宙航行アカデミー 準メンバー
国連宇宙週間 理事
国際月面天文台協会 理事
登録情報
- 出版社 : ダイヤモンド社 (2018/5/10)
- 発売日 : 2018/5/10
- 言語 : 日本語
- 単行本(ソフトカバー) : 264ページ
- ISBN-10 : 4478068100
- ISBN-13 : 978-4478068106
- 寸法 : 13.2 x 1.8 x 18.8 cm
レビュー
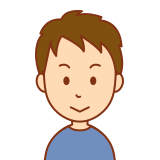
驚くことばかり
とても興味をそそられるタイトル。
すでに世界のBig5のIT企業が巨額を投資、宇宙を目指し、火星移住、宇宙旅行の実現へ向けて、手つかずの黄金を目指していると。
平凡な毎日や、海外旅行にあき、新しい世界に興味がある人におすすめします。
今までは不可能とされていた、宇宙ステーションの建設ならびに移住、地球と宇宙をエレベーターでむすぶ夢の階段など。スケールの大きさに圧倒されます。
著者は、JAXAで勤務し、コンサルタントとして宇宙企業のプロジェクトに参画されている方です。
2016/9、スペースX創業者、イーロン・マスクは壮大な計画を発表。今後10数年以内に地球~惑星間を数千人で輸送、40年~100年後には火星で100万人を居住地にすると・・・。
あと、残りの人生では宇宙旅行は無理と考えていたが、先がみえてきた。長生きして死ぬまでに1回はいきたい!
しかし、旅行代がすごい金額・・・。
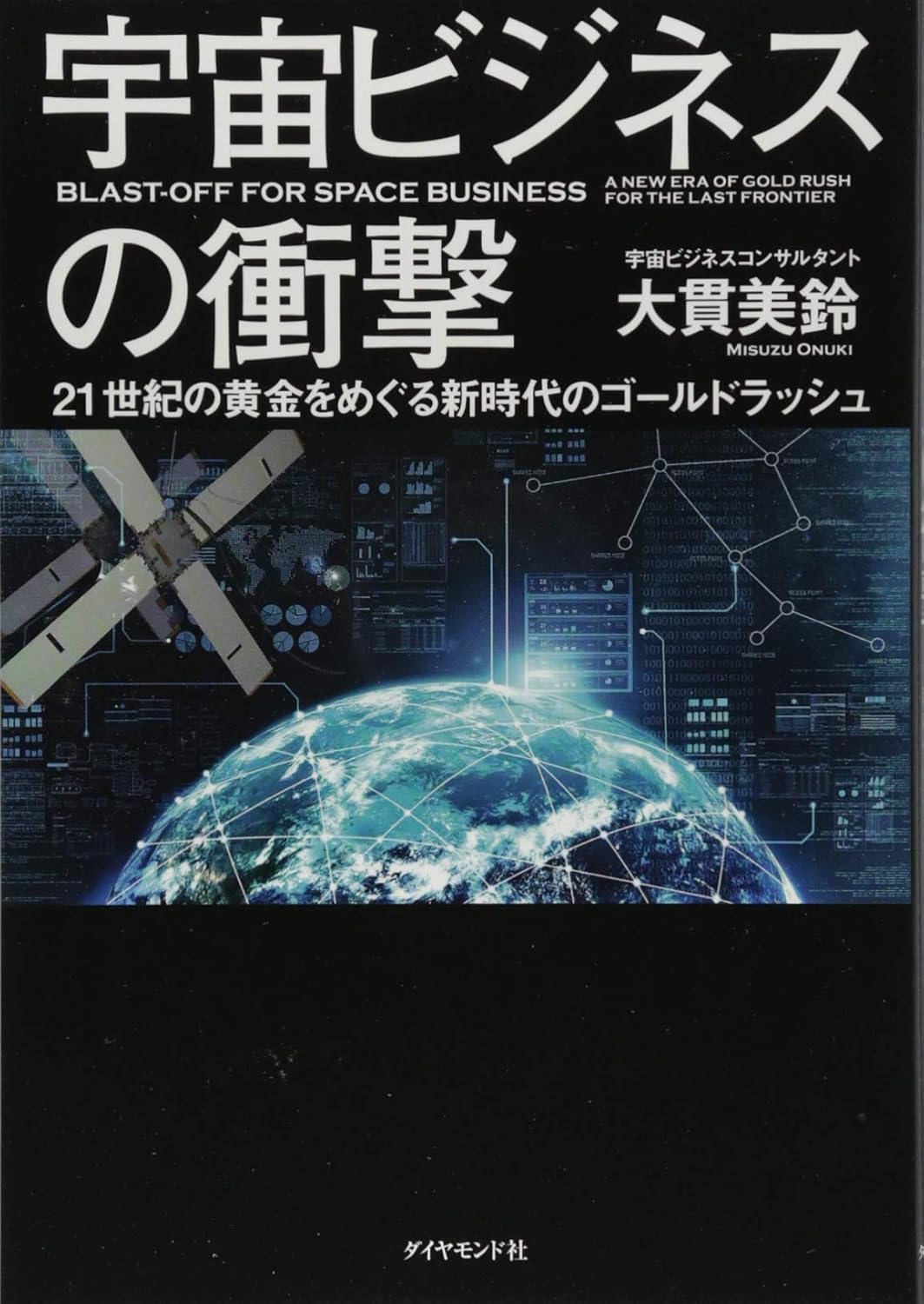


コメント