中国の旧暦と日本の旧暦(天保暦)の間には、以下の理由からずれが生じる可能性があります。
1.基準となる経度の違い
旧暦は月の満ち欠けに基づいていますが、その計算には天体の観測が必要です。中国と日本では、かつて基準となる経度が異なっていたため、わずかな時間のずれが生じることがありました。これにより、新月や朔の瞬間が異なる場合があり、暦の日付にずれが生じることがあります。
2.閏月の挿入規則の差異
旧暦では、季節とのずれを調整するために閏月が挿入されます。この閏月の挿入規則は、中国の旧暦と日本の旧暦で完全に同一ではありませんでした。そのため、同じ年でも閏月が入る月が異なる、あるいは閏月自体が入らないといった違いが生じることがあります。
3.歴史的な改暦
日本では明治時代にグレゴリオ暦に移行しましたが、それ以前に使用されていた天保暦は、中国の暦を参考にしながらも独自の改良が加えられていました。そのため、時代が下るにつれてずれが大きくなる可能性がありました。
ずれの程度について
具体的なずれの大きさは、年や月によって異なります。数日程度のずれが生じることもあれば、場合によっては1ヶ月程度のずれが生じることもあります。特に、閏月が挿入される年にはずれが大きくなる傾向があります。
旧暦変換のプログラムを検証しいると以下の問題にぶち当たり、よもや月が消えるなどと想像すらしていなかったので2日悩みました。

2033年は従来の方法で旧暦を計算すると、9月か10月が消えてしまうのです。そのためカレンダーを作るあらゆる人たちは、それぞれの解釈で旧暦を計算します。六曜は旧暦の日付によって決められるため、よって2033年は、カレンダーによって六曜が違うという事態が発生します。
現在、中国で一般的に使われているのはグレゴリオ暦ですが、旧暦も伝統的な行事や祝祭日(春節など)の決定に用いられています。日本でもグレゴリオ暦が主流ですが、一部の伝統行事や暦注には旧暦が参考にされることがあります。
まとめ
中国の旧暦と日本の旧暦の間には、基準となる経度の違いや閏月の挿入規則の差異などにより、ずれが生じる可能性があります。
そのずれの程度は一定ではなく、年や月によって変動します。
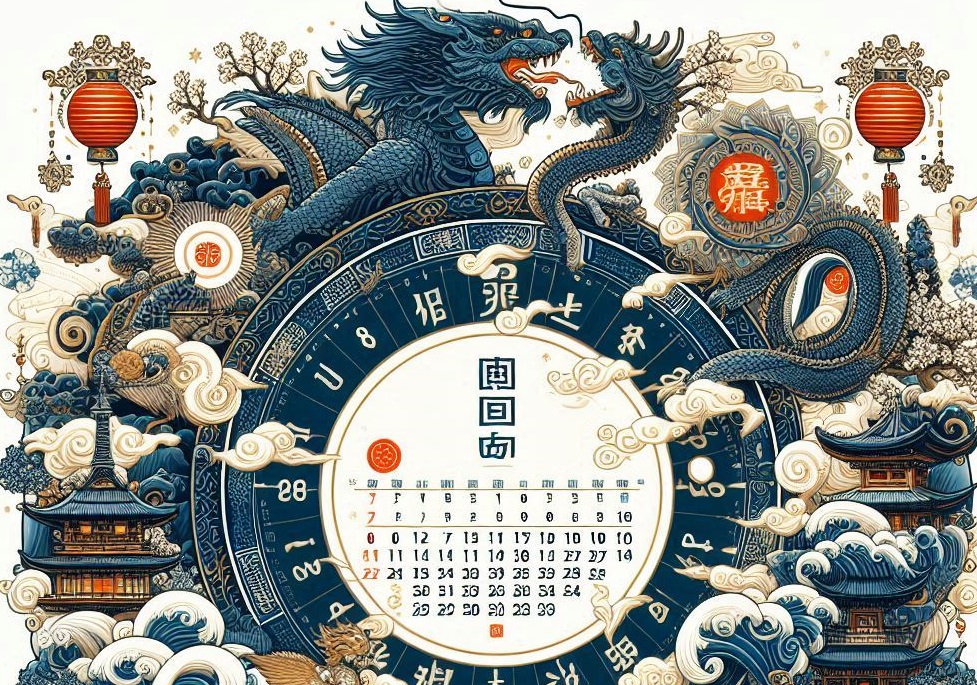


コメント