正義とは何かという根源的な問いに対し、「トロッコ問題」という究極の選択肢を提示し、一人を犠牲にすれば五人を救える状況で、その一人を殺すべきかを問いかけています。また、日本の累進課税制度の公平性や、過去の世代の過ちに対する現代の私たちの償いの義務についても問いかけ、正義についての意見が分かれることを示唆しています。
本書の著者であるマイケル・サンデルは、これらの問いを通じて、私たち自身の道徳観や倫理観に基づいて判断を下す必要性を提起しています。正義には唯一の正解はなく、価値観によって判断基準が異なると強調しています。異なる価値観とぶつかった場合に、どのように答えを導き出すべきかという問いも投げかけています。
ハーバード大学の超人気講義を書籍化した本書は、「正義」をめぐる哲学的思考の旅を通じて、現代社会が直面する倫理的ジレンマに斬り込みます。サンデル教授が提示する「正義の3つのアプローチ」とその批判的検証、そして新たな共同体主義的視点の核心を解説します。
第1部:正義をめぐる3つの思想的潮流
1. 功利主義
ジェレミー・ベンサムの功利主義は以下のようにまとめることができます。
- 功利主義の中心概念
道徳の基本原理は幸福すなわち快楽に対する苦痛の割合を最大化することであるとされます。この考え方は、ジェレミー・ベンサムによって確立されました。 - 正しい行いとは、快楽を生み出し苦痛を避けるもの、つまり効用を最大化するものです。
- 功利主義の目的
幸福(快楽)の総量を最大化することにあります。言い換えれば、より多くの人々に喜びをもたらし、苦痛を少なくする行為が正しいと判断されます。 - 功利主義の観点から見ると、例えば、4人が死ぬよりも1人が犠牲になった方が望ましいという考え方があり得ます。これは、全体の幸福の総量を増やすという点で評価されます。
- 功利主義の大きな弱点
個人の権利を尊重しない点が挙げられます。満足の総和だけを重視するあまり、個人を踏みつけにしてしまう場合があるのです。 - 1884年のイギリス船の遭難事件の例では、生き残った3人が雑用係の一人を食料にした行為が紹介されています。功利主義の観点からは、4人全員が死ぬよりも1人が犠牲になった方が望ましいとされますが、これは個人の権利や尊厳を軽視するという批判を生む可能性があります。
ベンサムの功利主義は、最大多数の最大幸福を追求する考え方であり、行為の道徳性は、その行為がもたらす快楽と苦痛の総量によって判断されます。しかし、この考え方は、個人の権利や少数意見を軽視する可能性があるという重要な課題を抱えています。
- 核心思想:最大多数の最大幸福を追求
- 具体例:医療資源の優先配分で「より多くの命を救える選択」を是とする
- 限界:
➔ 個人の権利を多数者の利益に犠牲にさせうる(例:拷問の正当化)
➔ 幸福の「質」を無視(快楽の量的比較のみ)
2. 自由至上主義(リバタリアニズム)
自由至上主義(リバタリアニズム)は以下のようにまとめることができます。
- 個人の自由の絶対性
リバタリアン(自由至上主義者)の中心的な主張は、どの人間も自由への基本的な権利を有しているということです。これは、功利主義が全体の幸福のために個人の権利を制限する可能性を重視するのとは対照的です。 - 政府の役割の限定
リバタリアンの考えは、経済効率を主な目的とはしておらず、人間の自由の名において制約のない市場を支持します。彼らは、安全のためのシートベルト着用義務のようなパターナリズム、売春や同性愛の禁止といった冒涜的法律、そして富裕層への課税などの所得や富の再分配を拒否します。 - 自己所有権の重視
政府による富の再分配に反対する背景には、リバタリアンが持つ自己所有権という概念があります。彼らは、自分が自分を所有しているならば、自分の労働やその成果も所有していると考えます。 - 課税への反対
この自己所有権の考え方から、政府が強制的に所得の一部を徴収することは、自分が政府に所有されていることになるという理屈になります。 - 個人の自由の限界
しかし、リバタリアンの自己所有権の考え方が及ぶ範囲については、全てが容易に容認されるわけではありません。例えば、臓器の売買、患者の自殺幇助、合意の上での食人などが自己所有権から認められるのであれば、それらも全て容認されることになってしまうという点が指摘されています。 - 功利主義との対比
功利主義が全体の幸福の最大化を重視するのに対し、リバタリアニズムは個人の自由という権利を最優先します。功利主義が多数の利益のために少数個人の権利を犠牲にすることを許容する可能性があるのに対し、リバタリアニズムは個人の権利は不可侵であると考えます。
自由至上主義は、個人の自由を至上の価値とし、政府の介入を最小限に抑えた社会を理想とする考え方です。その根幹には、自己の身体と財産に対する絶対的な所有権という概念が存在します。
- 核心思想:個人の自由と自己所有権の絶対化
- 具体例:自発的合意による臓器売買の容認
- 限界:
➔ 格差拡大を必然化(「自己責任」論の暴走)
➔ 共同体の絆や相互扶助を軽視
3. カントの義務論
カントの義務論は、行為の「結果」ではなく「動機」を重視する。正義にかなった行動とは、「義務の動機」(有用性や利便性ではなく、それが正しいから行うという理由)によってのみ導かれるべきだと主張する。例えば、嘘をつかない義務は、嘘の結果が良くても悪くても守られるべきであり、他者の評価や社会的利益とは無関係である。
- 核心思想:理性に基づく普遍的な道徳法則の遵守
- 具体例:嘘をつかない義務(結果を問わない)
- 革新性:人間を「目的そのもの」と扱う
- 限界:
➔ 感情や文脈を排除した過度に抽象的な倫理
第2部:サンデルの批判的検証
「無負荷の自己」概念への痛撃
- リベラリズムが想定する「共同体から切り離された個人」は虚構
- 現実の人間は常に「物語的アイデンティティ」を有する(家族・地域・歴史との絆)
市場原理主義への警告
- 市場が倫理を侵食する具体例:
➔ 妊娠代行サービスの商品化
➔ 戦争の民間委託(傭兵産業) - 「お金で買えるもの・買ってはいけないもの」の境界線喪失
「正義」は善き生の議論抜きに成立しない
- リベラル中立性の欺瞞:国家は必ず特定の「善の概念」を促進している
- 例:同性婚合法化論争は「結婚の本質とは何か」という根本的議論を避けられない
第3部:共同体主義的アプローチ
アリストテレス的「目的論」の再評価
- 制度の目的を問い直す:
➔ 大学は「学位販売店」か「知性を磨く場」か
➔ 軍隊は「職業」か「市民的義務」か
「共通善」を育む市民的討論
- 具体的事例で育む倫理感覚:
➔ 徴兵制 vs 志願兵制:平等の意味を問い直す
➔ 環境政策:将来世代への責任の所在
美徳の政治学
- 正義の実現に必要な3要素:
- 物語的連帯(歴史的継承性の自覚)
- 相互承認(差異を超えた対話の不断の実践)
- 公共性の再構築(市場原理に支配されない市民空間)
現代社会への示唆
1. 格差問題の再定義
- 単なる「再分配」論を超え、「何が価値ある活動か」を問う必要性
- 例:介護労働の低賃金は「社会が真に尊重する価値」を反映しているか
2. テクノロジー倫理
- 遺伝子編集・AI発展に伴う根本的問い:
➔ 「設計可能な人間」は共同体の絆をどう変容させるか
➔ アルゴリズムが「正義」を決定することの危険性
3. 多文化主義の限界
- 文化相対主義の行き詰まり:
➔ 女性割礼を「文化の違い」で容認できるか
➔ 普遍的人権と伝統的慣習の衝突点
正義の探求は終わらない
サンデルが最終的に提示するのは「正解」ではなく、「共に考え続けるプロセス」そのものの重要性です。コロナ禍のワクチン配分、気候変動対策、AI倫理といった現代課題に直面する私たちに必要なのは
- 倫理的想像力(他者の立場で考える力)
- 公共的理性(感情論を超えた建設的討論)
- 市民的勇気(不確実性の中でも判断し行動する覚悟)
本書が喚起する真の問いは、「正しい社会」の設計図ではなく、「私たちはいかなる共同体を築きたいのか」という不断の自己省察に他なりません。
著者について
マイケル・サンデル(Michael J. Sandel) 1953年生まれ。ハーバード大学教授。専門は政治哲学。ブランダイス大学を卒業後、オックスフォード大学にて博士号取得。2002年から2005年にかけて大統領生命倫理評議会委員。1980年代のリベラル=コミュニタリアン論争で脚光を浴びて以来、コミュニタリアニズム(共同体主義)の代表的論者として知られる。類まれなる講義の名手としても著名で、中でもハーバード大学の学部科目“Justice(正義)”は延べ14,000人を超す履修者数を記録。あまりの人気ぶりに、同大は建学以来初めて講義を一般公開することを決定。日本ではNHK教育テレビ(現Eテレ)で『ハーバード白熱教室』(全12回)として放送されている。著書『これからの「正義」の話をしよう』は世界各国で大ベストセラーとなり、日本でも累計100万部を突破した。ほかに『それをお金で買いますか』『ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業』(以上早川書房刊)などの著作がある。2018年10月、スペインの皇太子が主宰するアストゥリアス皇太子賞の社会科学部門を受賞した。
レビュー
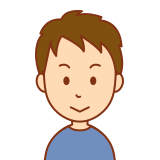
本書は、正義とは何か?という問いに対し、次の3つの視点から説明している。
①最大多数の最大幸福(効用や福祉の最大化を目的にした功利主義的な見方)
②選択の自由(市場を重視する自由至上主義的な立場と、リベラルな平等主義者とで立場が別れる)
③美徳と共通善
現代において正義をめぐる議論は、効用や自由を中心に行われているが、
本書ではそれらについて功利主義や自由至上主主義における伝統的な議論を踏まえた上でその限界を示す。
そういった正義における考え方の限界を乗り越えるために、美徳や共通善からのアプローチが必要だと著者のマイケル・サンデルは説く。
本書を読んで良かったことは、正義における様々な立場を理解することができたこと。
この本の目的としては、正義をめぐるいくつもの考察を経ることで、自分自身がこれまで漠然と抱いてきた見解を批判的に見るということだと思う。
効用の最大化も、選択の自由も、必ずしも道徳や正義にかなう結論には至らない場合もあり、
「この考えが正解」という万能薬は無く、時代や状況に合わせて共通の善や美徳を追求するという考え方も大事だと感じた。
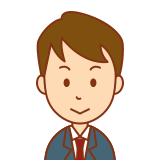
考え抜く力を育てる一冊
マイケル・サンデル教授の専門は政治哲学で、ハーバード大学で
教えるようになって三十年以上です。
正義と銘打った講義を設けたら大変人気が出て、これまでに
14,000人以上の人が履修しました。この一冊は、長年にわたる
講義を元に構築されています。
哲学ですから、書かれたというより積みあがっている感じがします。
例示も具体的で、カントやアリストテレスなど、誰もが知っている
思想家からの引用も多いです。
名前は聞いたことはあるけれど、中身はよく知らないという人が
多いのではないでしょうか。
大学の講義がベースなので平易とは言えない部分もありますが、
素人でも手に取れるようかみ砕かれています。
多面的に議論を展開しているので、哲学の入門書としても
最適です。
第一章は「正しいことをする」
ここから議論が始まります。
メキシコ湾で発生したハリケーンの被害により、電気が止まり、
屋根の上に木々が倒れかかり、緊急避難的にモーテルで
寝泊まりするはめになった人がいました。
ところが、そこで請求された金額が法外なふっかけだったのです。
あえて法外なふっかけと書きました。
市場原理主義者なら、需要と供給に則っただけとの考えに
なるでしょう。業者にしてみれば、大量のバックオーダーを抱え、
作業条件も悪く作業員の確保もままならないわけですから、
不当な金額を請求したわけではないとの思いもあるでしょう。
正しい価格とは何でしょうね。
古代から現代まで、脈々と受け継がれる哲学を学ぶ必要性が
言及されています。
正義と権利、義務と同意、名誉と美徳、道徳と法。
政治哲学者は、このような理念について考え抜いているのです。
わたしは、市場原理ですべて決まる的な考え方に違和感を持って
いましたし、事件があった時にまき起こる自己責任という言葉も
気になっていました。そんな感覚に考え方を示してくれる本でした。
理想通りにいかないことはいっぱいあります。
この本を読んで、心が少し整理されました。
答えは一つではないかもしれませんが、考えることが大事ということが
伝わりました。
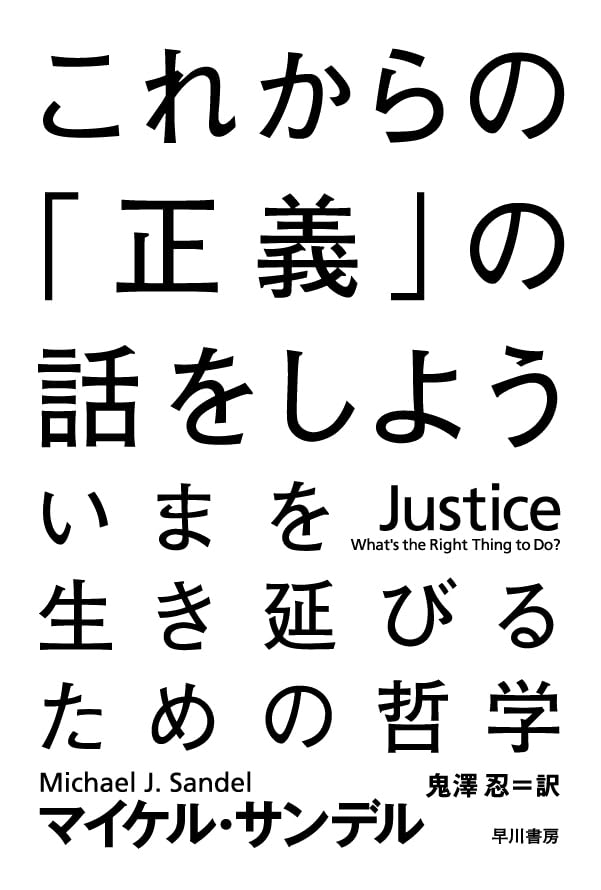


コメント