10代、20代前半は様々なジャンルの本を乱読し、幅広い知識を得ることができました。20代後半になると、仕事に関連する本や趣味である数学や物理の本を中心に読書を続け、最低でも年に30冊を目標にしていました。
しかし、30歳を過ぎたあたりで、同期のコミュニケーション能力に関して疑問を抱くようになりました。何か言っていることが幼く感じられ、説明も小学生の頃のような擬音を多用し、感覚では理解できていると思っていましたが、本当に意思疎通ができているのか不安を感じることが増えました。この不安を解消するために、「最近読んで面白かった本は何ですか?」と尋ねることにしました。少し期待もありましたが、確認も含めた疑問をぶつけると、返ってきた答えは「中学以降マンガ以外読んでいない」というものでした。この回答から、本を読まない社会人がいることに驚き、思い返すと言葉に重みがないことにも納得できました。
この経験から、読書は単に情報を得る手段ではなく、言葉の使い方や表現力を磨く重要な方法であることを再認識しました。読書を通じて得られる知識はもちろん大切ですが、それ以上に、その知識をどのようにコミュニケーションに活かすかが重要だと感じました。言葉に重みを持たせるためには、質の高い読書を続けることが不可欠であり、自分自身の言葉の使い方を見直すきっかけにもなりました。
今後も読書を続けることで、自分自身のコミュニケーション能力を高め、より深い意思疎通ができるよう努力していきたいと思います。読書は知識を広げるだけでなく、言葉の使い方や表現力を磨くための貴重な手段であることを再認識し、今後も質の高い読書を心掛けていきます。
解像度の高い人と低い人の比較
ビジネスにおいては、顧客の課題と競合との差の解像度を上げることが特に重要であると述べられています。顧客が抱える課題を正確に把握し、競合と比較して自社の強みや差別化ポイントを明確にする必要があります。
| 特徴 | 解像度の高い人 | 解像度の低い人 |
|---|---|---|
| 全般的な理解 | 物事を深く理解している状態。物事がくっきりと見えている。思考、発言、行動が具体的になる。成功しやすい。物事をうまく進めるための最も重要なポイントに気づくことができる。 | 物事の理解が浅い状態。思考がふわっとしている、ピンと来ないと言われることがある。発言がまとまりがない、トンチンカンになることがある。物事の重要なポイントがわからない。 |
| 深さ(行動と理解) | 一つの現象を深く詳細に把握している。課題を解決するために具体的な行動を起こし、自分の目で見て、現場で話を聞くなど、リアルな情報を重視する。行動した後、なぜそうなったのかを深く考え、改善策を模索し、再び行動するサイクルを回す。粘り強く課題に取り組み続ける。 | 一つの現象に対する理解が表面的。課題の原因を単純に捉えがち(例:痩せないのは食べ過ぎ)。具体的な行動に移せない、または行動しても思考が伴わないため、学びが少ない。一度や二度の失敗であきらめやすい。リアルな情報を得るための行動を怠りがち。 |
| 広さ(知識と視野) | 幅広い知識を持っている。ダイエットを例にすると、様々な運動の選択肢を知っている。本を読んだり、人の話を聞いたりして、新しい情報に積極的に触れる。語彙力が豊富で、様々な分野の人と円滑に情報交換ができる。多くの選択肢の中から、自分に合った最適な方法を見つけやすい。 | 知識の幅が狭い。ダイエットの方法が走る、ジムで鍛えるなど、限られた選択肢しかない。新しい情報に触れる機会が少ない。語彙力が不足しているため、物事を細かく捉えたり、異なる分野の人と深いコミュニケーションを取ることが難しい場合がある。 |
| 構造(言語化と整理) | 自分の頭の中で考えていることを言語化し、図に分かりやすくまとめることができる。自分の考えを紙やメモなどに書き出すことで、何を理解していて、何が理解できていないのかを明確にする。ロジックツリーやマインドマップなどのツールを活用する。複雑な事柄も簡潔に図示化できる。 | 頭の中で考えていることをうまく言語化したり、整理したりすることが苦手。千と千尋の神隠しのストーリーなど、複雑な内容を説明しようとしても、全体像が曖昧でうまく伝えられないことがある。自分の理解度を客観的に把握することが難しい。 |
| 時間(過去と未来) | 過去の事例や歴史について知っており、人がどのような失敗をしてきたのかを理解しているため、同じようなミスを避けることができる。時代の変化を予測し、将来を見据えた上で効果的な打ち手を模索する。 | 過去の失敗から学びにくく、同じような過ちを繰り返す可能性がある。現在のことしか考えず、将来の 변화に対する意識が低い場合がある。 |
| ビジネス視点 | 顧客が抱える課題を正確に把握し、その解決策を提供できる。競合他社の状況を詳細に分析し、自社の強みや差別化ポイントを明確に理解している。ビジネスの状況を簡潔に表現できる(例:フェルミ漫画大学の説明)。 | 顧客の課題を表面的なレベルでしか理解できない場合がある。競合他社の状況を把握せず、独自性や競争優位性を打ち出せない可能性がある。ビジネスの状況をうまく説明できない。 |
| 行動のタイミング | ある程度解像度が高まったら、時間をかけすぎずに実際に行動に移すことを重視する。目的は課題解決であり、分析や検討に時間を費やしすぎること(お尻博士になること)を避ける。 | 十分な理解が得られないまま行動に移せない、または完璧な理解を得ようとして行動が遅れる傾向がある。 |
解像度の低い人の特徴
- 物事の理解が浅い状態です。
- 仕事の話をしている時に、相手から「ふわっとしていますね」とか「ピンと来ないです」、「結局は何が言いたいんでしょうか」と指摘されることがあります。
- 発言がまとまりがない、トンチンカンになることがあります。
- 物事の重要なポイントがわかりません。
- 課題の原因を単純に捉えがちです(例:痩せないのは食べ過ぎ、といった表面的で一つだけの原因で考えがちです)。
- 課題を解決するための具体的な行動に移せないことがあります。
- 行動しても、なぜそうなったのかを深く考えないため、学びが少ない傾向があります。
- 一度や二度の失敗であきらめやすいです。
- リアルな情報を得るための行動(現場に行く、話を聞くなど)を怠りがちです。
- 知識の幅が狭いです。ダイエットの方法が走る、ジムで鍛えるなど、限られた選択肢しか持ち合わせていないことがあります。
- 新しい情報に触れる機会が少ないです。
- 語彙力が不足しているため、物事を細かく捉えたり、異なる分野の人と深いコミュニケーションを取ることが難しい場合があります。
- 自分の頭の中で考えていることをうまく言語化したり、整理したりすることが苦手です。
- 複雑な内容(例:映画のストーリーなど)を説明しようとしても、全体像が曖昧でうまく伝えられないことがあります。
- 自分の理解度を客観的に把握することが難しいです。
- 過去の失敗から学びにくく、同じような過ちを繰り返す可能性があります。
- 現在のことしか考えず、将来の変化に対する意識が低い場合があります。
- ビジネスにおいては、顧客の課題を表面的なレベルでしか理解できない場合があります。
- 競合他社の状況を把握せず、独自性や競争優位性を打ち出せない可能性があります。
- ビジネスの状況をうまく説明できません。
- 十分な理解が得られないまま行動に移せない、または完璧な理解を得ようとして行動が遅れる傾向があります。
本を読む人と読まない人の比較
| 特徴 | 本を読む人 | 本を読まない人 |
|---|---|---|
| 知識の幅 | 幅広い知識を持っている。様々な分野の本を読むことで、多様な情報や視点に触れることができます。 | 限られた範囲の知識しか持たない傾向があります。 |
| 情報への接触度 | 積極的に新しい情報に触れる。本を読むことが新しい情報を得る主要な手段の一つとなります。 | 新しい情報に触れる機会が少ない傾向があります。 |
| 選択肢の多さ | 問題解決や目標達成のための選択肢を多く持つ傾向があります。ダイエットを例に挙げると、様々な方法を知っている。 | 問題解決や目標達成のための選択肢が限られている場合があります。ダイエットの場合、限られた方法しか知らないことがあります。 |
| 語彙力 | 語彙力が豊富になる傾向があります。新しい言葉を覚え、より細かく世界を認識することができます。 | 語彙力が不足している場合があり、物事を細かく捉えたり、異なる分野の人と深いコミュニケーションを取ることが難しいことがあります。 |
| 世界の認識度 | 語彙力が増えることで、世界をより細かく、多様な視点から認識できる可能性があります。 | 世界を認識する際の解像度が低く、表面的な理解にとどまる可能性があります。 |
| 他者とのコミュニケーション能力 | 様々な分野の言葉や知識を持つことで、異なるバックグラウンドを持つ人と円滑なコミュニケーションを取ることができる可能性があります。 | 語彙力や知識の不足により、異なる分野の人との情報交換がうまくいかない場合があります。 |
| 問題解決のアプローチ | 過去の事例や他者の経験(書籍から得られる)を参考に、多様なアプローチで問題解決に取り組むことができる可能性があります。 | 問題解決のアプローチが限定的になりがちで、既存の方法に固執する可能性があります。 |
| 特定分野への理解度 | 特定の分野について書かれた本を読むことで、その分野に関する深い知識や理解を得ることができます。不動産の例では、オーナーの本を読むことで知識が深まります。 | 特定の分野に関する知識や理解が不足しがちです。不動産の知識はオーナーに直接聞くなどの限られた手段に頼ることが考えられます。 |
| 解像度(広さの視点) | 解像度を構成する「広さ」の視点が高いと言えます。幅広い知識を持つことで、物事を多角的に捉え、より多くの選択肢の中から最適なものを選ぶことができます。 | 解像度を構成する「広さ」の視点が低いと言えます。知識の幅が狭いため、視野が狭くなり、限られた選択肢の中からしか考えられない可能性があります。 |
| 学習意欲 | 積極的に知識を吸収しようとする意欲が高いと考えられます。自ら情報を求め、学習する習慣があると言えます。 | 学習意欲が低い場合や、受動的な情報収集にとどまる可能性があります。 |
| 思考の柔軟性 | 多様な情報に触れることで、固定観念にとらわれにくく、柔軟な思考を持つことができる可能性があります。 | 情報の偏りなどにより、思考が硬直化し、新しい視点を受け入れにくい可能性があります。 |
| 自己成長意欲 | 本を読むことを通して、自己の知識や能力を高めようとする意欲が高いと考えられます。 | 自己成長への意識が低い場合や、具体的な行動に移しにくい可能性があります。 |
個人メモ
要約:思考の「解像度」を高める4つの視点
- 深さ(Depth)
- 一つの現象をどこまで深く詳細に把握しているかを指します。深さを高めるには、実際に行動し、自分の目で見て、現場で話を聞くといったリアルな情報を得ることが重要です。うまくいかなかった場合は、なぜそうなったのかを考え、新しい打ち手を試し、それを繰り返すことで理解を深めます。また、深さを得るには粘り強く行動し続けることが必要であり、最初のそこそこのアイデアにたどり着くまでに少なくとも200時間、その検証にさらに200〜400時間程度の活動が必要だとされています。
- 目的
表面的な理解を脱し、本質を捉える - 行動法
- 「なぜ?」を5回繰り返す(5Why分析)
- 専門用語や前提を疑い、定義を明確化する
- 具体例と抽象概念を行き来する(例:事象→理論→実践)
- 訓練方法
- 行動する → 考える → 行動するを繰り返す
課題に対して仮説を立てたら、まず実際に行動してみます - 行動の結果を思考する
行動してみてうまくいかなかった場合は、「なぜこうなったのか」「どうすればいいのか」を深く考え、新たな打ち手を検討します - 再び行動する
考えた新しい打ち手を実際に試してみます2 …。このサイクルを繰り返すことで、物事の核心に迫る深い理解が得られます。 - 粘り強く行動し続ける
一度や二度の挑戦で諦めず、少なくとも200時間は情報収集、思考、行動に費やすことを意識しましょう5 。良いアイデアや本質的な原因にたどり着くには、時間と根気が必要です
- 行動する → 考える → 行動するを繰り返す
- 広さ(Breadth)
- 幅広い知識を持つことを指します。広さを高めるには、とにかく本を読んで人の話を聞き、新しい情報に触れることが重要です。語彙力が増すと、世界をより細かく見ることができ、様々な分野の人との情報交換が円滑になります。
- 目的
視野狭窄を防ぎ、多角的に考える - 行動法
- 異分野の知識や他者の視点を積極的に取り入れる
- 「逆説的思考」で反対意見を想定する(例:「これが間違いだとしたら?」)
- マトリクス図で複数の軸を比較する(例:重要度×緊急度)
- 訓練方法
- 本を読む
自分の課題に関連する分野だけでなく、様々なジャンルの本を読むことで、多様な視点や解決策を知ることができます。著者は、課題に関連する業界の本を端から端まで買うことを勧めています5 。 - 人の話を聞く
異なるバックグラウンドを持つ人々と積極的にコミュニケーションを取り、新しい情報や考え方に触れましょう。語彙力を高めることも、より深い情報交換に繋がります
- 本を読む
- 構造(Structure)
- 自分で考えていることを言語化し、図に分かりやすくまとめることを指します。頭の中で考えていることを紙に書き出し図にすることで、自分が何を理解していて、何が理解できていないのかを把握することができ、理解が深まります。ロジックツリーやマインドマップなどの図を活用することが推奨されています。
- 目的
情報を整理し、関係性を可視化する - 行動法
- マインドマップやロジックツリーで階層化する
- 要素を「MECE(漏れ・ダブりなく)」に分解する
- 因果関係を矢印で結び、フィードバックループを描く
- 訓練方法
- 頭の中で考えていることを言語化する
漠然とした考えを言葉にすることで、内容を明確にし、理解を深めます - 図にする
言語化した考えを、ロジックツリーやマインドマップなどの図で整理します。図にすることで、自分が何を理解していて、何が理解できていないのかを視覚的に把握できます。何も見ずに図にできるレベルになれば、その事柄を深く理解できている証拠です
- 頭の中で考えていることを言語化する
- 時間(Time)
- 過去や歴史について知り、時代の変化を踏まえた上で効果的な打ち手を模索することを指します。人がどのように失敗してきたのかを知ることで、同じようなミスを減らすことができます。また、自分たちのいる業界の未来を予測することも重要です。
- 目的
過去・現在・未来の時間軸で思考を拡張する - 行動法
- タイムラインを作成し、経緯や未来予測を記す
- 「10分後・10年後」の影響を比較する(短期vs長期視点)
- 定期的に進捗を振り返り、仮説を更新する
- 訓練方法
- 過去の事例や歴史を学ぶ
過去の成功例だけでなく、失敗例から学ぶことで、同じ過ちを繰り返すリスクを減らすことができます。先人たちの経験を知ることは重要です - 未来を予測する
自分がいる業界や社会全体の変化を予測し、将来を見据えた上で効果的な打ち手を考えましょう。人口減少や技術革新など、時代の流れを把握することが重要です
- 過去の事例や歴史を学ぶ
効果的な実践ステップ
- 問題定義
「何を解決すべきか」を4視点で洗い出す - 情報収集
深さ(専門資料)+広さ(多様な情報源)でインプット - 構造化
ロジックツリーで要素を分解し、優先順位をつける - 時間軸検証
短期アクションと長期戦略を分けて計画 - 反復改善
PDCAサイクルで思考の解像度を継続的に向上
重要な気づき
- 「曖昧さ」は思考の解像度不足が原因
4視点を使い分けることで、霧のかかった思考が「8K映像」のように鮮明になる - 「完璧」より「改善」
解像度は一気に上げるのではなく、小さな修正を積み重ねる - アウトプット前提の思考
他人に説明するつもりで整理すると、自然に解像度が上がる
応用例
- ビジネス: 複雑な課題を「構造×時間」で戦略化。
- 学習: 「深さ×広さ」で暗記から本質理解へ。
- 人生設計: 「時間軸×構造」で理想の未来を逆算。
思考の解像度を高めれば、「迷いが減り、意思決定が速く・確実に」なります。まずは1つの視点から試してみてください。
最後に、解像度がある程度高まったら、時間を使いすぎずに実際に行動に移すことが大切だと強調されています。解像度を上げることはあくまで課題解決の手段であり、目的化してしまうことを避けるべきです。
著者について
馬田隆明
東京大学 FoundX ディレクター。
University of Toronto 卒業後、日本マイクロソフトを経て、2016年から東京大学。東京大学では本郷テックガレージの立ち上げと運営を行い、2019年からFoundXディレクターとしてスタートアップの支援とアントレプレナーシップ教育に従事する。スタートアップ向けのスライド、ブログなどで情報提供を行っている。著書に『逆説のスタートアップ思考』『成功する起業家は居場所を選ぶ』『未来を実装する』。
書籍情報
- 出版社 : 英治出版 (2022/11/19)
- 発売日 : 2022/11/19
- 言語 : 日本語
- 単行本(ソフトカバー) : 352ページ
- ISBN-10 : 4862763189
- ISBN-13 : 978-4862763181
- 寸法 : 21 x 14.8 x 2.1 cm
レビュー
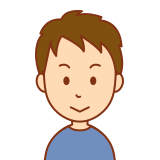
思考の解像度を高めて曖昧さを突破する
本書は、思考や情報収集、行動の質を向上させるための「解像度」という概念を中心に据え、スタートアップやビジネスの現場での実践知をもとに書かれています。「深さ」「広さ」「構造」「時間」という4つの視点を軸に、曖昧さを明確にするための具体的なアプローチが解説されています。
思考の解像度を上げるためには単に情報を集めるだけでは不十分で、それをどのように整理し、構造化するかが重要だという指摘が印象的でした。ビジネスやプロジェクトの進行中によく直面する「ふわっとした」課題を解決するために非常に役立つと感じました。
また、著者がスタートアップの現場で培ったノウハウを基にしているため、現実的かつ実践的な内容が多いことも本書の魅力です。具体例や行動指針が豊富で、読み進める中で自分の思考の進め方や情報整理の方法を見直すきっかけとなりました。
内容はスタートアップやビジネスの現場向けにやや特化している印象がありますが、思考の精度を上げたいと考えるすべての人にとって、有意義なヒントが詰まった一冊だと思います。
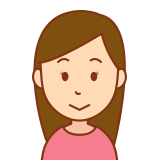
解像度を上げる4つ「深さ」「広さ」「構造」「時間」について
取り組んでいることの解像度が足りないため、どうしたらはっきり見えるようになるのかを知りたくて、藁をも掴む思いで手にした本です。同時期に読んだ『具体・抽象トレーニング』(細谷功著)の方が一読ですっと腹落ちして、この後に読んだ本書はすぐに事例を使ってワークをしてみるも、実際の運用度は最初はあまり良いものではありませんでした。
しかし、数ヶ月後、ノンフィクションである『A Story of the World in 6 Glasses』を読んだときに、その構成の素晴らしさに、本書で語っている4つの視点「深さ」「広さ」「構造」「時間」の中で「深さ」が最重要である意味が深く理解でき、点と点が繋がって初めて腹落ちしました。『A Story of the World in 6 Glasses』は世に出ている飲み物の歴史を綴っていますが、それだけにとどまらず取り上げている飲み物が科学・哲学・文化・政治・金融取引に及んだ話を軽妙に物語のように語っています。小説を読んでいるように面白かったことから、「深さ」「広さ」「構造」「時間」4視点の大切さが解像度を上げるためにいかに大切で、その中でも「深さ」が一番重要であることがよく判り、「広がり」過ぎず、「構造化」して「時間軸」をしっかりすれば、これほど解像度が上がるのだと、頭の中でハリーポッターで出てきた動く階段が絶妙に組み合わさりそれぞれの寮のドア前に導いたような脳内になりました。
「具体」「抽象」で言うと、本書は「抽象」で、具体例として『A Story of the World in 6 Glasses』が助けになりました。”ああ、そうかこうやって話を組み合わせたり、組み立てればいいんだ”と思わず膝を打ちました。
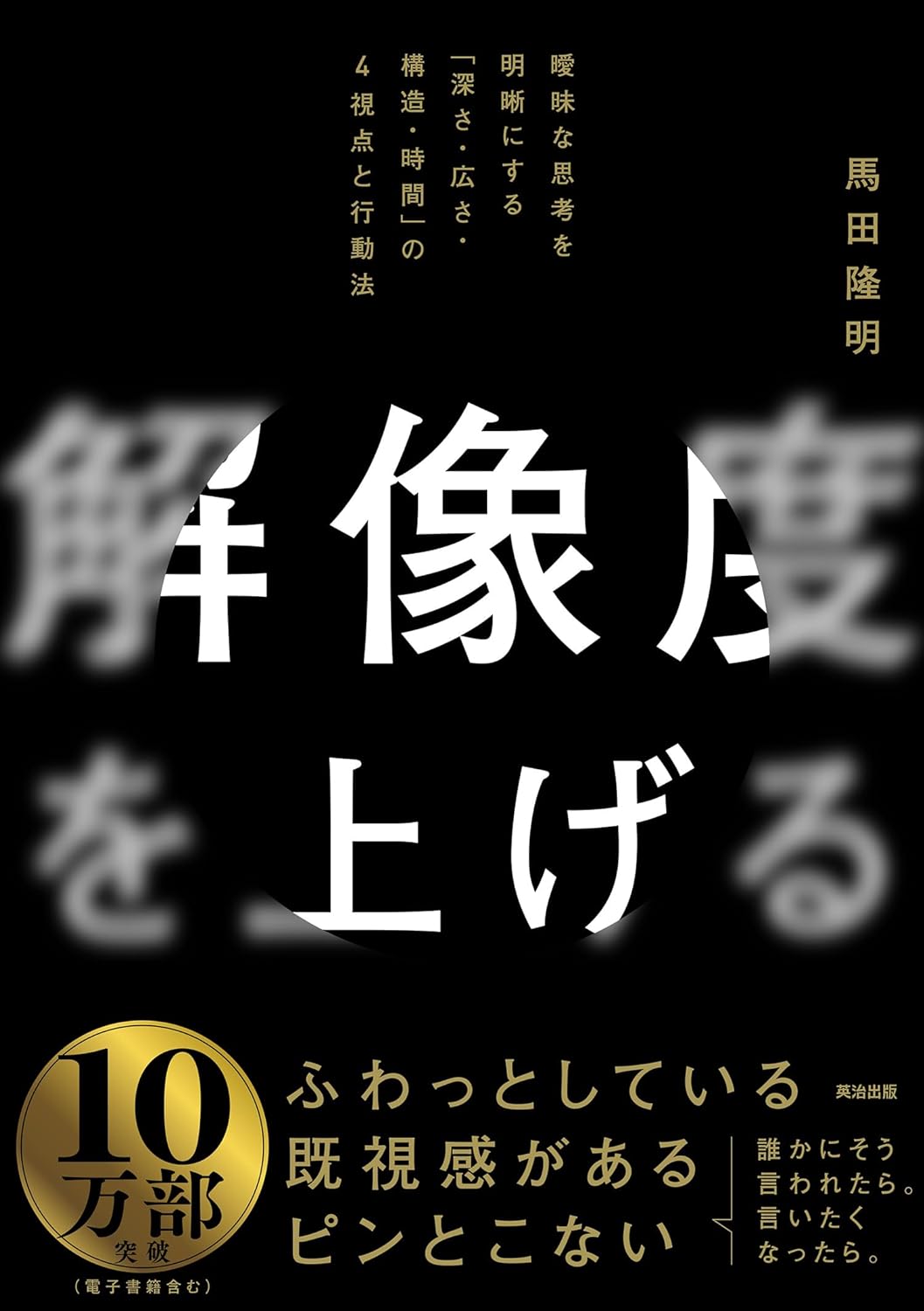


コメント