人口減少と高齢化、それに伴う労働市場や物価の変化を理解し、自身の働き方や消費行動を見直すことが、これからの時代を生きる上で重要な備えとなるでしょう。
日本の人口減少は危機ではなく、成熟社会への進化プロセスです。江戸時代の日本が世界最高水準の循環型社会を築いたように、現代の日本はデジタル技術と伝統的価値の融合で新たな社会モデルを提示できるはずです。鍵は「量から質への転換」「画一から多様性への移行」「拡大から持続可能性へのシフト」にあります。
今後日本で確実に起こると予測される5つの事柄が提示されています。
- 人手不足はますます深刻になる
女性の就業率は既に高く、高齢者の労働参加にも限界があるため、労働力不足は構造的な問題として深刻化すると予想されます - 賃金はさらに上昇する
人手不足が深刻化する中で、企業は人材を確保するために賃上げを余儀なくされ、賃金競争が起こると考えられます - 労働参加は限界まで拡大する
年金制度への不安や物価上昇などを背景に、高齢者を中心に労働市場への参加意欲が高まり、企業側も柔軟な働き方を提供するようになると予想されます - 優先順位の低いサービスは消失する
人手不足や労働コストの上昇により、過剰なサービスは維持できなくなり、本当に必要なサービスに絞り込まれていくと考えられます。例えば、運送業の再配達サービスの有料化や、飲食店でのセルフサービス化などが考えられます - 緩やかなインフレーションが定着する
人手不足による賃金上昇は企業のコスト増となり、製品やサービス価格への転嫁が進むと予想されます。また、これまでのデフレマインドも変化していく可能性があります
結論として、日本の経済は人口減少と高齢化という大きな構造変化に直面しており、それが労働市場や消費構造、企業のあり方に大きな影響を与えています。賃金上昇や労働時間短縮は、人手不足という背景の中で進む必然的な流れであり、今後、日本はこれまで経験したことのない新しい経済状況を迎えることになると解説されています。企業や個人はこれらの変化を理解し、適切に対応していくことが重要であると強調されています。
人口減少と高齢化の加速がもたらすもの
日本の経済と社会の根幹を揺るがす人口減少と高齢化の加速です。
- 日本の人口は2007年をピークに減少しており、今後その減少速度は増していくと予測されています。
- 主要先進国と比較しても、日本の人口減少は特に急速に進んでいます。
- 同時に、生産年齢人口(15歳から64歳)が減少し、高齢者(65歳以上)の割合が急速に増加しています。特に、85歳以上の超高齢者の割合が顕著に増加すると見込まれています。
この人口構造の変化は、経済のあらゆる側面に深刻な影響を与えます。働く人の数が減り、消費を担う人も減少するため、経済成長の足かせとなるのはもちろんのこと、社会保障制度の維持にも大きな課題が生じます。人口減少は経済や社会のあらゆる面に大きな影響を与え、働く力や使われるお金の量に大きく関わると強調されています。
この人口減少と高齢化という避けられない現実を背景として、日本の労働市場では以下のような変化が起きており、今後さらに加速すると考えられます。
- 深刻な人手不足の慢性化。
- 女性の就業率は既に高い水準にあり、これ以上の大幅な増加は期待しにくい状況です。
- 高齢者の労働参加も進むと考えられますが、健康上の問題などから限界があります。
- 地方や中小企業を中心に、賃金を上げても人材が集まらないという絶対的な人手不足が顕在化しており、全体として、これまでの低い賃金水準では労働力を確保できなくなっているという相対的な人手不足が主な問題となっています。
- 人手不足は一時的な現象ではなく、日本の未来に大きな影響を与える構造的な問題であり、日本経済の新しい常識になりつつあると指摘されています。
- 賃金の上昇傾向の継続。
- 人手不足が深刻化する中で、企業は人材を確保するために賃上げを余儀なくされるでしょう。
- 優秀な人材を確保しようとする企業間の賃金競争が起こり、賃金上昇の波は業界全体、そして労働市場全体に広がっていくと予想されます。
- これまでの労働力を安価に調達するというモデルは、少子高齢化が進む日本ではもはや成立せず、賃金は自律的に上昇するフェーズに入ると考えられています。
- 労働時間の急速な短縮。
- 働き方改革関連法の影響や、労働者のワークライフバランスを重視する意識の高まりにより、労働時間は減少傾向にあります。
- 特に若い世代の労働時間の減少が顕著です。
- 労働時間の短縮は、たとえ年収が прежний 水準でも、実質的な時給の上昇につながっています。
消費行動の変化
今後の日本において消費行動には以下のような変化が考えられます。
- 医療・介護サービスの需要増加
高齢者の割合が増加するため、医療や介護といったサービスへの需要がますます高まるでしょう。特に85歳以上の超高齢者の割合が急増すると予想されており、これらのサービスへの依存度が高まると考えられます。 - 消費の二極化
比較的若い高齢者は多様な消費活動に積極的に参加する一方で、年齢が上がるにつれて医療・介護サービスへの需要が急増すると予測されています。これにより、消費の重点が年齢層によって大きく異なる可能性があります。 - サービスの選択とコスト意識の向上
人手不足と労働コストの上昇により、これまでのような手厚いサービスを維持することが難しくなり、優先順位の低いサービスは消失する可能性があります。例えば、運送業における個別配送の見直しや、飲食店でのサービス簡略化などが考えられます。このような変化に伴い、消費者は本当に必要なサービスを見極め、それに見合ったコストを支払うという意識が高まるでしょう。 - 生活必需品への支出増加の可能性
緩やかなインフレーションが定着すると、日用品や食料品などの価格が上昇し、家計におけるこれらの支出の割合が増える可能性があります。 - テクノロジーを活用した消費行動
人手不足を補うために、AIやロボットを活用したサービスが普及する可能性があります。消費者は、これらの新しい技術を取り入れたサービスを積極的に利用することで、効率的な消費行動をとるようになるかもしれません。
これらの変化は、人口構成の変化、労働市場の動向、そして経済全体の状況が複雑に絡み合って起こると考えられます。消費者は、これらの変化を理解し、自身のライフスタイルや価値観に合わせて、より賢い消費行動をとることが求められるようになるでしょう。
労働時間の短縮は企業の経営に何をもたらすか?
否定的な影響として、まず挙げられるのは、人件費の増加や業務の効率化の必要性の高まりです。これまで長時間労働を前提としていた企業では、労働時間が短縮されることで、同じ業務量をこなすために人員を増やす必要が生じ、人件費が増加する可能性があります。また、限られた時間内で成果を上げる必要が生じるため、業務プロセスの見直しや効率化が求められます。
一方、肯定的な影響も存在します。法令を遵守している企業にとっては、残業が減ることで人件費を削減する機会にもなります。また、労働時間が短縮されることで、従業員一人ひとりの労働生産性が向上する可能性があります。限られた時間で一定の成果を上げる必要があるため、優先度の低い業務を削減し、結果として平均的な生産性が向上することが期待できます。
さらに、短時間労働者が増えることで、企業は業務をより細分化し、効率的な働き方を模索するようになります。
労働時間が短縮されれば、長時間労働を前提としていた企業では人件費の増加や業務の効率化が課題となると指摘されています。一方、法令に準拠する企業にとっては、残業が減ることで人件費を削減できる可能性があるとも述べられています。また、労働時間の短縮は労働生産性にも影響し、限られた時間で成果を出す必要から生産性が向上する可能性があると説明されています。
今後、週休3日制などが注目されるように、社会全体で柔軟な働き方を求める動きが広がっており、企業は高齢者や短時間労働を希望する人々が働きやすい環境を整備していく必要が出てきます。タスクの細分化が進めば、AIやロボットが業務の一部を担うようになり、人間はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになる可能性も示唆されており、これによって社会全体の生産性向上が期待されています。
著者について
1985年生まれ。リクルートワークス研究所研究員・アナリスト。一橋大学国際公共政策大学院公共経済専攻修了。厚生労働省にて社会保障制度の企画立案業務などに従事した後、内閣府で官庁エコノミストとして「経済財政白書」の執筆などを担当。その後三菱総合研究所エコノミストを経て、現職。著書に『ほんとうの定年後――「小さな仕事」が日本社会を救う』(講談社現代新書)、『統計で考える働き方の未来――高齢者が働き続ける国へ』(ちくま新書)がある。
レビュー
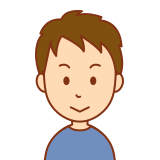
日本の社会は間違いなく定常的な人手不足(労働市場が構造的な供給制約)へと向かう。
その際、安易に外国人労働者を大量に受け入れとしまえば、日本人の賃金抑制、
非効率企業の延命、過当競争の継続など、日本経済の高度化を妨げてしまう。
そうではなく、機械による自動化、省力化と本来の人間ならではの仕事を効率的に
組み合わせた日本社会の高度化を推し進めれば、賃金の上昇と市場供給力が向上し、
非効率企業の退出による新陳代謝といった好循環が進んでいくと予想している。
やはり、少子高齢化で日本経済が縮小するというだけの悲観論ではなく、より高度な
日本社会が実現していく好機と見做せる、という本書には大いなる希望が見いだせる。
【追記】
根源に立ち返り、「個人の尊厳、自由と平等」を最優先にするならば、
それが日本の人口減少に歯止めをかけることにはなりえないと考える。
国力が、労働人口の多寡に依存する時代はとうに過ぎ去ったと思うからである。
人が、国力などということを意識せず、働きたいように働き、産みたいように産む。
それが本来の必然の姿であろう。
国内の一人当たり実質年収は下がり続けているが(1997年430.5万円、
2023年369.5万円)、これは実質賃金が上がらない以上に、総労働時間が
減少していることにもよる(2000年1839時間、2022年1626時間)。
先進国中最も急激な減少過程にあり、既に米国を下回り、このままいけば
伊(1563時間)、英国(1516時間)を下回る勢いである。
頑張って残業してでも仕事をこなす、から、短時間で効率よく、あるいは高齢や
パートで短時間労働をより好む層の増加もある。
これからの慢性的、構造的な労働力不足の中で、(無節操に国民を貶める移民政策を
取らなければ)、間違いなく時給は上昇していく。
短時間働いても高い賃金となれば、労働生産性は向上することになる。
少子高齢化は、デメリットのみではなく、これからは賃金上昇のための非常に重要で、
不可欠の要素となるのではないか。
この過程で必要なのが、低賃金で働かせることによって利益を得ている企業の退出と
新分野で人材を効率よく活かす企業の増加による新陳代謝である。
その中で、自動化、省力化とヒトの力を巧く協調しながら全体として効率よく仕事を
進めて行く。これこそが日本社会の高度化につながっていくための基本構造である。
こうした環境が整えば、自ずと婚姻率、出生率も増えていくであろう (但しそれは、
減少率の低下に留まるであろうが) 。
日本は、民族、宗教間対立がなく、民度も高く文化が均質で、国境が海で守られている。
社会基盤が一通り整い、安全で清潔、高い品質の製品や商品が容易に手に入り、
故障もせず正確に運行される公共交通機関などなど、世界的にもまれな住み易い国
となっている。
これこそが世界の中で日本が社会高度化を進め得る最先端の地位にあることのベース
ともなっている。今やこれを活かしていく絶好のチャンスと言えるのではないか。
その実現可能性は十二分にあろう。
今回の選挙でも、これまで自公のみでろくに審議もせず強行採決されていたものが、
(国民民主党が寝返らなければ)何事も国会での議論なくしては通らなくなったのも
ひとつの進歩である。
即ち、大局的に眺めれば、日本は何とかいい方向に向かいつつある、というのは
楽観的に過ぎないであろうか。
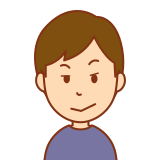
「ほんとうの定年後」に続く名著
同じ著者の「ほんとうの定年後」が良かったので、本書も読みました。前著同様、しっかりしたデータ、取材に基づき論を進めていく姿勢は、説得力が高い。全体に、正攻法の視点で書かれているので、共感する部分が多く、これからの日本の在り方を考える上でとても参考になります。
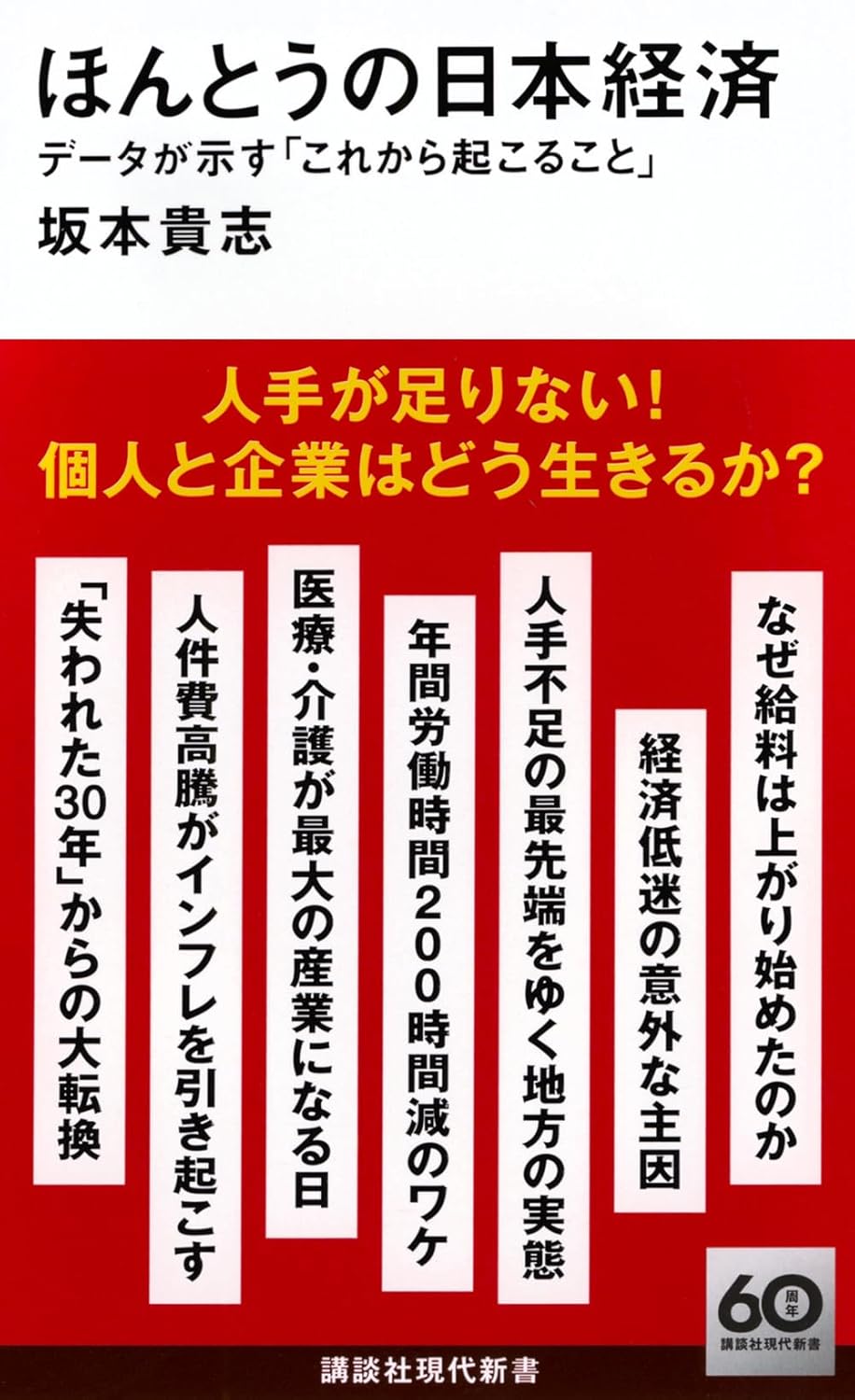


コメント