ICL(Implantable Collamer Lens)は、強度近視・角膜薄い人にとって最適な矯正法ですが、高額な費用と長期的な白内障リスクが課題です。将来的には老眼矯正機能の追加で需要が拡大すると予測されます。
Hole ICLは術前のレーザー虹彩切開術(LPI)が不要でレンズ中央に穴(360μm)が開き、房水の流れを確保されるために眼圧が上がるリスクが少なく安全性も高いです。
ICLとは?
ICL(アイシーエル)は、眼内(虹彩と水晶体の間)に特殊なレンズを挿入する屈折矯正手術
- 正式名称はImplantable Collamer Lens(インプラント可能なコラマーレンズ)。
- 素材は生体適合性の高い「コラマー」(コラーゲンとポリマーの複合材)を使用。
- 特徴
- 角膜を削らず、レンズを追加するため可逆的(レンズを摘出可能)
- 強度近視(-20Dまで)・乱視(-6Dまで)に対応
- 永続的矯正が可能(レンズ寿命はほぼ半永久的)
ICLが向いている人
- 強度近視・乱視でレーシックでは矯正できない高度数(-10D超)
- 角膜が薄い人は角膜切削が不要なため、レーシック不適応者に適す
- ドライアイが心配な人は角膜神経を傷つけないため、術後ドライアイリスクが低い
- 20歳以上で眼球の成長が終了していることが条件
- 将来の選択肢を残したい人はレンズ摘出で元の状態に戻せる
ICLが向かない人
- 前房深度が浅いは虹彩と水晶体の間のスペース不足(2.8mm未満は不可)
- 緑内障・白内障のある人は眼圧上昇や併発リスクが高まる
- 角膜内皮細胞数が少ないは術後角膜の透明性維持に支障が出る可能性
- 妊娠中・授乳中はホルモンバランスの変化で検査値が不安定
- 自己免疫疾患は術後の炎症リスクが高い
ICLのメリット
- 強度近視に最適は-20Dまで矯正可能(レーシックの約2倍)
- 可逆的でレンズを摘出すれば元の状態に戻せる
- ドライアイリスク低で角膜を削らないため、術後ドライアイが少ない
- 高画質・高コントラストでハロー現象がレーシックより軽微
- 回復が早いため1〜2日で視力が安定
ICLのデメリット
- 高額
両眼で50〜100万円(レーシックの2〜3倍) - 白内障リスク
水晶体への接触で、術後数十年で発症する可能性 - 定期検査が必要
眼圧・角膜内皮細胞の経過観察が必須 - 合併症リスク
感染症・緑内障・瞳孔ブロック(稀) - 矯正範囲の限界
老眼には非対応(多焦点レンズは開発中)
ICLのリスク
- 白内障が5〜10年後に発症リスクが約5%上昇
- 眼圧上昇がレンズ挿入直後に一時的に起こる可能性
- 感染症が術後1週間以内の細菌性眼内炎が0.1%未満
- 角膜内皮細胞減少が長期使用で細胞数が徐々に減少
- レンズずれで外傷などで位置が稀ではあるがずれる場合
ICLとレーシックの比較
| 項目 | ICL | レーシック |
|---|---|---|
| 矯正方法 | 眼内レンズ挿入 | 角膜レーザー切削 |
| 適応度数 | -20Dまで | -10Dまで |
| 可逆性 | あり(レンズ摘出可能) | 不可逆的 |
| ドライアイリスク | 低い | 高い(約30%が慢性化) |
| 費用 | 50〜100万円 | 20〜40万円 |
| 合併症 | 白内障・緑内障 | ハロー現象・角膜混濁 |
| 回復期間 | 1〜2日 | 1週間 |
ICLの費用
手術費用:片眼25〜50万円、両眼50〜100万円(検査費・術後ケア含む)
- 内訳
- レンズ代:20〜40万円(片眼)
- 手術技術料:10〜20万円(片眼)
- 保険適用:自由診療(全額自己負担)
ICLの世界的利用状況
2023年時点で、全球の屈折矯正手術の約15%を占める(レーシックは70%)
- アジア
強度近視人口が多い中国・韓国・日本で普及 - 欧米
FDA(米国)・CE(欧州)認可済み
レーシックに比べ利用率は低いが、適応外患者の選択肢として拡大中
ICLの今後
- 技術革新
- 多焦点ICLで老眼矯正機能を追加(臨床試験中)
- 調整可能レンズで術後の度数変更が可能なレンズ開発
- 適応拡大
- 前房深度の浅い患者向けの薄型レンズ
- 小児への適応研究(現状は20歳以上が原則)
- 安全性向上
- 角膜内皮細胞保護のためのレンズデザイン改良
- AIを用いた術前シミュレーションの精度向上
Hole ICL(EVO ICL)
Hole ICLは「EVO ICL」とも呼ばれ、中央に穴(CentraFLOWテクノロジー)が開いた最新モデルです。
| 比較項目 | Hole ICL(EVO ICL) | 通常のICL |
|---|---|---|
| レンズデザイン | 中央に穴(360μm)が開き、房水の流れを確保 | 穴なし(房水循環が制限される) |
| 主な目的 | 眼圧上昇・瞳孔ブロックのリスク低減 | 強度近視・乱視の矯正 |
| 適応範囲 | – 近視:-0.50D 〜 -20.00D – 乱視:-0.50D 〜 -6.00D | – 近視:-3.00D 〜 -20.00D – 乱視:-1.00D 〜 -6.00D |
| 前房深度の必要最小値 | 2.8mm(従来より狭いスペースでも適応可能) | 3.0mm |
| 白内障リスク | 低い(房水循環が改善され、水晶体への接触軽減) | やや高い(長期使用でリスク上昇) |
| 瞳孔ブロックリスク | ほぼなし(穴が房水の通り道を確保) | 稀にある(術後ピロカルピン点眼が必要な場合も) |
| 術後検査の頻度 | 年1回(安定後) | 年1〜2回(眼圧・角膜内皮の厳密な経過観察) |
| 眼圧管理 | 不要(自然な房水循環) | 必要(術後の眼圧上昇に注意) |
| レーザー虹彩切開術(LPI) | 不要 | 必要(瞳孔ブロック予防のため) |
| 費用(両眼) | 70〜100万円(従来ICLと同程度) | 60〜100万円 |
| FDA承認状況 | 2022年承認済み(米国) | 2005年承認済み |
| 日本での承認状況 | 2020年承認 | 2007年承認済み |
| 視力の安定性 | 術後1〜2日で安定 | 術後1〜2日で安定 |
| ドライアイリスク | 低い(角膜切削なし) | 低い(角膜切削なし) |
| 老眼矯正機能 | 非対応(多焦点ICLは開発中) | 非対応 |
| レンズの交換可能性 | 可能(将来的な度数変更時) | 可能 |
房水循環とリスク低減
- Hole ICLは中央の穴が房水の流れを自然に保ち、瞳孔ブロック(房水が詰まり眼圧が急上昇する状態)をほぼ解消。これにより、術前のレーザー虹彩切開術(LPI)が不要
- 通常のICLはLPIが必要な場合があり、術後の眼圧管理に注意が必要
適応範囲の拡大
Hole ICLは前房深度が2.8mmと浅い患者でも適応可能(通常ICLは3.0mm以上必要)
白内障リスクの低減
Hole ICLあ房水循環の改善により、水晶体への代謝ストレスが軽減。長期使用時の白内障発症リスクが低下(従来比約30%減)
承認状況と普及率
- Hole ICLは日本では2020年承認され、2023年現在でICL手術の約70%を占める
- 通常のICLは安定した実績があるが、Hole ICLに置き換わりつつある
Hole ICLの評価
- Hole ICLのメリット
- 瞳孔ブロック予防のため安全性が向上
- 前房深度が浅い患者にも適応可能
- 術前のレーザー処置(LPI)が不要
- 通常のICLの残る利点
- 強度乱視用のトーリックICLのバリエーションが豊富
- 長期的な臨床データが蓄積されている

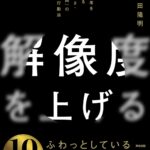

コメント