トランプ政権が日本の自動車および自動車部品に対して25%の追加関税を課すという仮定のシナリオに基づき、日本および米国経済に及ぼす多角的な影響を分析するものである。
データに基づく定量的な評価と、サプライチェーンや産業構造に及ぶ質的な分析を組み合わせ、両国が直面するであろう経済的・戦略的課題を網羅的に解明することを目的とする。
エグゼクティブ・サマリー
- 日本経済への影響: 25%の追加関税は、日本の自動車産業に壊滅的な打撃を与え、日本経済全体を景気後退に陥れる深刻なショックとなる。複数のシンクタンクの試算によれば、日本の実質GDPは0.2%から0.5%程度押し下げられると予測される。自動車メーカーの利益は大幅に圧縮され、その影響は部品、素材、物流など広範なサプライチェーンに波及する。これにより、国内で
数万人規模の雇用が失われるリスクが現実のものとなる。この政策は、日本の製造業の「空洞化」を加速させ、政府および企業に対し、米国市場への過度な依存からの脱却と、抜本的なサプライチェーンの再構築という戦略的転換を強いることになる。 - 米国経済への影響: 米国にとって、この関税政策は「両刃の剣」となる。国内の自動車労働者、特にラストベルト地帯の支持層に向けた保護主義的なメッセージとしての政治的意味合いは強いものの、経済的合理性は低い。日本車をはじめとする輸入車の価格は大幅に上昇し、
米国の消費者に直接的な負担を強いることになる。さらに、GMやフォードといった米国の自動車メーカーも、日本や世界各国から多数の部品を輸入しており、関税によって
生産コストが上昇し、国際競争力が削がれるというパラドックスに直面する。インフレ圧力の増大、限定的な雇用創出効果、そして同盟国との関係悪化といった代償を伴うため、その正味の経済的便益は極めて疑わしい。 - 戦略的含意: 日本にとっての最大の課題は、この地政学的リスクを前提としたサプライチェーンの多様化と強靭化、そして対米輸出自主規制(VER)の再来も視野に入れた高度な通商外交の展開である。一方、米国にとっては、保護主義的な公約と、グローバル化した自国産業の現実および消費者利益との間の矛盾をどう解決するかが問われる。この関税は、世界の自動車産業のサプライチェーンを分断し、長期的には日米双方の経済的厚生を損なう可能性が極めて高いと結論付けられる。
第1章:礎となる数値:日米自動車貿易の現状
1.1 日本の貿易構造と米国の位置づけ
分析の前提として、まず日本経済における貿易、特に米国との貿易関係の規模と構造を正確に把握することが不可欠である。これらの数値は、25%という高率の関税が単なる一品目への課税ではなく、日本経済の根幹を揺るがしかねない規模の衝撃であることを示している。
財務省の貿易統計によると、2024年の日本の輸出総額は過去最高の107兆879億円に達した。このうち、最大の輸出相手国は米国であり、その額は21兆2947億円と、日本の総輸出額の19.9%を占める。第2位の中国(18兆8624億円、17.6%)と合わせると、日米中3カ国で日本の輸出の半分以上を占める構造となっており、特に米中両国への依存度の高さが際立っている。
一方で、2024年の日本の貿易収支は3兆8,990億円の赤字であったが、これは前年から赤字幅が縮小した結果である。この貿易赤字という背景は、後述する為替レートの変動を分析する上で重要な要素となる。
1.2 日本経済の基幹、自動車産業
自動車産業は、名実ともに関係省庁や業界団体が指摘するように、日本経済を支える基幹産業である。その経済規模は他を圧倒している。
経済産業省の工業統計調査によれば、2022年における自動車製造業の製造品出荷額等は約62.8兆円に達し、これは全製造業の17.4%を占める巨大な規模である。
さらに重要なのは、その雇用の裾野の広さである。自動車産業は、完成車メーカーだけでなく、鉄鋼、化学、ガラス、繊維、電子部品といった素材・部品メーカーから、販売、整備、輸送、金融、保険に至るまで、極めて広範な関連産業によって支えられている「総合産業」である。日本自動車工業会(JAMA)の推計によると、これらの自動車関連産業全体の就業人口は
約558万人に上り、これは日本の全就業人口(約6747万人)の8.3%に相当する。
この産業構造の特異な集中は、地方経済においてより顕著に現れる。例えば、トヨタ自動車の本社が所在する愛知県豊田市では、2022年の製造品出荷額等のうち実に92.8%を自動車関連産業が占め、市内工場の従業者の77.1%が同産業に従事している。これは、自動車産業への打撃が、単なるマクロ経済指標の悪化に留まらず、特定の地域経済を崩壊させかねない深刻なリスクを内包していることを示唆している。
1.3 米国市場への依存構造
この日本経済の屋台骨である自動車産業が、いかに米国市場に深く依存しているかを定量的に理解することが、本分析の核心である。
2024年、日本から米国への輸出総額21.3兆円のうち、自動車およびその部分品の輸出額は7.2兆円に達した。これは、対米輸出全体の33.8%を占めており、他のいかなる品目をも大きく引き離す最大の輸出品目である。この7.2兆円という数字は、日本の2024年の輸出総額(107.1兆円)の約6.7%に相当する。
さらに、2023年の日本の自動車関連輸出総額が21.6兆円であったことを踏まえると、米国市場だけでその
約3分の1を稼ぎ出している計算になる。この一点集中の構造が、トランプ政権の関税政策に対する日本の脆弱性の根源となっている。
| 指標 | 金額・数値 | 構成比・備考 |
| 日本の総輸出額 | 107.1兆円 | 過去最高 |
| 日本の対米輸出額 | 21.3兆円 | 総輸出額の19.9% |
| 日本の対米自動車・部品輸出額 | 7.2兆円 | 対米輸出額の33.8% |
| 自動車関連産業の就業人口 | 558万人 | 全就業人口の8.3% |
| 自動車製造業の製造品出荷額 | 62.8兆円 (2022年) | 全製造業の17.4% |
これらのデータが示すのは、単なる貿易関係の強さではない。それは、「日本経済は自動車産業に依存し、その自動車産業は米国市場に依存する」という二重の依存構造である。この構造は、平時においては日本経済の強みとして機能してきたが、米国の保護主義的な通商政策という外生的なショックに対しては、極めて脆弱なアキレス腱となる。一つの市場、一つの政策変更が、日本の産業全体、ひいては国民生活にまで連鎖的な影響を及ぼす伝達経路が、ここに明確に存在している。
さらに、この巨大な輸出フロー(7.2兆円)が滞ることは、日本の貿易収支に直接的な影響を与え、為替レートの変動要因となる。輸出の急減は、円を売ってドルを買う実需(輸入代金支払い)に対し、ドルを売って円を買う実需(輸出代金受け取り)を減少させるため、理論上は円安圧力となる。通常、円安は輸出企業にとって追い風となるが、25%という関税の壁の前ではその効果は限定的とならざるを得ない。むしろ、エネルギーや食料品の輸入価格を押し上げ、国内のインフレを助長するという副作用の方が強く意識されるだろう。このように、関税の一次的影響(輸出減少)が、為替変動という二次的影響を引き起こし、それがまた別の複雑な経済的帰結をもたらすという、多層的なフィードバックループの存在が示唆される。
第2章:日本経済への衝撃波:多角的影響分析
25%の追加関税が発動された場合、その衝撃は自動車メーカーを震源地として、サプライチェーン全体、そしてマクロ経済全体へと津波のように波及していく。本章では、その影響の連鎖を多角的に分析する。
2.1 自動車メーカーへの直撃
関税の直接的な影響を最も受けるのは、言うまでもなくトヨタ、ホンダ、日産をはじめとする日本の自動車メーカーである。
- 利益の蒸発: 25%という関税率は、企業努力によるコスト吸収や、販売台数を維持したままでの価格転嫁が不可能なレベルである。自動車産業の専門家は、この関税によって日本の自動車産業全体の利益が約4割、金額にして2.7兆円近く減少する可能性があると試算している。また、野村総合研究所は、全産業ベースの経常利益が7.7%押し下げられると分析しており、影響の甚大さを物語っている。
- 生産・販売の急減: 米国市場での価格競争力を失った日本車は、大幅な販売減少を避けられない。これにより、米国向けに完成車を生産している国内工場の稼働率は著しく低下し、大規模な減産を余儀なくされる。
- 株価への影響: 金融市場は、こうした事態を即座に織り込む。過去の関税発動の懸念が高まった局面では、自動車メーカーやデンソー、アイシンといった主要部品メーカーの株価が急落した。TOPIX(東証株価指数)全体で見ても、8~9%の下落を記録した事例があり、市場がいかにこのリスクを深刻に受け止めているかがわかる。関税発動が現実となれば、日本株全体がリスクオフの渦に巻き込まれることは必至である。
2.2 サプライチェーンの連鎖反応
自動車産業の特性は、その広範な裾野にある。1台の自動車は約3万点の部品から構成されており、完成車メーカーの生産計画の変更は、ピラミッド構造をなすサプライチェーン全体に即座に影響を及ぼす。
完成車メーカーによる生産削減は、Tier1(一次下請け)の部品メーカーへの発注減に直結する。その影響は、Tier2(二次下請け)、Tier3(三次下請け)へと連鎖的に波及し、経営体力の弱い中小・零細企業ほど深刻な打撃を受ける。影響を受ける業種も、鉄鋼、非鉄金属、プラスチック、ゴム、ガラス、繊維、電子部品など、製造業のあらゆる分野に及ぶ。
このサプライチェーンへの打撃は、愛知県や静岡県、神奈川県といった自動車産業の集積地だけでなく、関連部品工場が立地する日本全国の地域経済を疲弊させる。日本自動車部品工業会(JAPIA)をはじめとする業界団体は、かねてよりサプライチェーン全体への深刻な影響を懸念し、政府に対して支援策を要請している。
2.3 マクロ経済への下押し圧力:定量的評価
個々の企業や産業への影響は、最終的に日本経済全体のマクロ経済指標を悪化させる。複数の主要シンクタンクがその影響を試算しており、その深刻さにおいて見解はほぼ一致している。
- GDPの縮小:
- 大和総研は、25%の自動車関税によって日本の実質GDPが0.36%押し下げられると試算している。野村総合研究所は、より直接的な影響を考慮し実質GDPを0.2%程度押し下げると分析。大和総研の別レポートでは、産業連関表を用いて川上・川下産業への波及効果まで含めると、その影響は-0.52%まで拡大する可能性があると指摘している。
- さらに、トランプ政権が示唆する「相互関税」が同時に発動された場合、GDPの押し下げ効果は最大で0.9%に達するとの試算もある。
| シンクタンク | GDP押し下げ効果(実質) | 主な前提・備考 |
| 大和総研 | -0.36% | 25%の自動車関税のみを想定 |
| 野村総合研究所 | -0.2% | 自動車・部品への25%関税を想定 |
| 大和総研 | -0.52% | 産業連関表を用い波及効果を含む |
| 野村総合研究所 | -0.9% | 25%自動車関税+相互関税が発動された場合 |
- 雇用の悪化:
- GDPの縮小は、必然的に雇用の減少を伴う。大和総研の試算では、国内の乗用車生産が10%減少した場合、1年後には5.4万人の就業者数が減少するとされている。
- 時事通信も、米国向け生産の大幅減により雇用が5万人程度減少するとの試算を報じており、影響の大きさは共通認識となっている。
- 為替レートの変動とスタグフレーションのリスク:
前述の通り、輸出の急減は円安要因となる。しかし、これは日本経済にとって諸刃の剣である。円安は輸入物価を押し上げ、特にエネルギーや食料品の価格上昇を通じて消費者物価を刺激する。景気が後退する中で物価が上昇する、いわゆる
スタグフレーションのリスクを高めることになる。金融政策も、景気後退に対応するための金融緩和と、円安によるインフレを抑制するための金融引き締めという、相反する圧力にさらされ、極めて難しい舵取りを迫られるだろう。
これらの分析が示すのは、25%の自動車関税が、単なる貿易問題に留まらない、日本経済の構造的な危機を引き起こすトリガーとなり得ることである。特に、この政策がもたらす最も深刻な長期的影響は、日本の製造業の「空洞化」(空洞化)の加速である。関税によって日本からの輸出が採算割れとなれば、企業は生き残りのために米国での現地生産を拡大せざるを得なくなる。これは、市場原理に基づく合理的な経営判断ではなく、政治的な圧力による強制的な生産移転である。その結果、国内の生産拠点は縮小・閉鎖され、高度な技術を持つ熟練労働者の雇用が失われ、地域経済は疲弊し、国内での研究開発や設備投資も停滞する。これは、日本の産業競争力の基盤そのものを長期にわたって蝕むことに他ならない。
この危機的な状況は、日本政府と産業界に戦略的な大転換を強いるだろう。短期的には、打撃を受ける国内サプライチェーンに対する大規模な財政支援や雇用対策が不可欠となる。そして中長期的には、米国市場の政治的リスクを再評価し、輸出先の多角化を国家戦略として強力に推進する必要に迫られる。EUやASEAN、インドといった他の経済圏との連携を深め、米国への一極集中から脱却する動きが加速することは避けられない。この関税は、戦後の日本の通商政策の根幹を揺るがし、新たな国際経済秩序の中での立ち位置を模索させる、歴史的な転換点となる可能性がある。
第3章:米国のジレンマ:関税という両刃の剣
トランプ政権が発動する自動車関税は、米国の国内産業を保護し、雇用を創出することを大義名分とする。しかし、その実態は複雑であり、米国経済にとっても多くの副作用と矛盾をはらむ「両刃の剣」である。本章では、その多面的な影響を分析する。
3.1 消費者と市場への影響
関税のコストは、最終的に米国の消費者が負担することになる。
- 車両価格の高騰: 25%という高率の関税は、輸入業者や販売店が完全に吸収することは不可能であり、その大部分が小売価格に転嫁される。例えば、これまで400万円(約2万5700ドル)で販売されていた日本車は、単純計算で510万円(約3万2900ドル)近くまで値上がりする可能性がある。これは、ただでさえ過去5年間で新車価格が21%上昇している米国市場において、消費者の購買意欲を著しく減退させる要因となる。
- 選択肢の減少と需要の減退: 価格が急騰した輸入車は市場での競争力を失い、消費者が選べる車種は大幅に減少する。特に、価格に敏感な層は新車購入を断念、あるいは先送りせざるを得なくなり、市場全体の販売台数が落ち込む「需要破壊」を引き起こす可能性がある。
3.2 国内産業のパラドックス
この関税政策の最大の皮肉は、保護対象であるはずの米国の自動車メーカー自身にも大きな損害を与える点にある。
- 「保護」の神話: GMやフォードといった米国の「ビッグスリー」は、もはや純粋な国内企業ではない。彼らのサプライチェーンは高度にグローバル化しており、エンジン、トランスミッション、電子部品など、多くの重要部品を日本を含む世界各国から輸入している。フォードは、米国内で生産する車両の部品の約6割を輸入に頼っており、この関税による損失額を年間2100億円(約14億ドル)と試算している。GMも同様かそれ以上の影響を受けると見られている。彼らは、部品コストの上昇分を自社で吸収して利益を削るか、価格に転嫁して販売台数を落とすか、という厳しい選択を迫られる。
- 「トランスプラント」への打撃: 日本の自動車メーカーは、長年にわたり米国での現地生産を拡大してきた。これらの「トランスプラント」と呼ばれる工場は、数十万人規模の米国人雇用を創出し、地域経済に深く根付いている。2024年にはトヨタだけで127万台を米国で生産している。しかし、これらの工場もまた、日本やメキシコなどから多くの基幹部品を輸入しており、サプライチェーンは国境を越えて複雑に絡み合っている。関税は、これらの効率的な生産体制を直撃し、米国工場のコストを押し上げ、結果的にその競争力を削ぐことになる。
| メーカー | 米国市場シェア(概算) | 北米現地生産比率(概算) |
| GM | 17% | 約50% |
| Toyota | 15% | 約70-80% |
| Ford | 13% | 約80% |
| Hyundai/Kia | 11% | 増加傾向 |
| Honda | 9% | 約99% |
| Stellantis | 8% | NAFTA依存高い |
| Nissan | 7% | 約57% |
| Tesla | 4% | ほぼ100%(米国) |
注:シェアは2024年の速報値や各種報道に基づく概算。現地生産比率は北米全体(米国・カナダ・メキシコ)での生産分が米国販売に占める割合の概算値。
この表が示すのは、「米国メーカー」もグローバルな部品輸入に依存し、「外国メーカー」が米国の主要な生産者・雇用主であるという、現代の自動車産業の現実である。この複雑な相互依存関係を無視した単純な関税政策は、意図せざる結果として自国の産業基盤をも傷つける。
3.3 経済全体への波及と政治的背景
自動車産業への影響は、マクロ経済全体へと波及する。
- インフレ圧力: 自動車は米国の消費者物価指数(CPI)において大きなウェイトを占める。自動車価格の全面的な上昇は、全体のインフレ率を押し上げる要因となる。ゴールドマン・サックスは、関税コストの6割が消費者に転嫁されると予測している。
- 雇用の純効果: この政策の政治的な狙いは、中西部のラストベルト地帯における製造業雇用の回復である。しかし、その効果は極めて不透明だ。デトロイトの工場で雇用が維持されたとしても、アラバマやケンタッキーにある日本メーカーの工場や、全米のディーラー網で雇用が失われれば、国全体での純増は限定的、あるいはマイナスになる可能性すらある。JPモルガン・チェース研究所の分析では、関税の影響を受ける企業にとって、そのコストは従業員一人当たり平均2,080ドルに相当すると試算されており、これは賃金凍結や解雇の圧力となることを示唆している。
- 関税収入の不確実性: トランプ政権は、この関税によって年間1,000億ドルの歳入増が見込めると主張した。しかし、これは輸入量が維持されることを前提とした皮算用である。関税が「成功」し、輸入が大幅に減少すれば、当然ながら関税収入もそれに比例して減少する。
これらの分析から浮かび上がるのは、この関税政策が米国の自動車産業内に戦略的な分裂を生み出すという構図である。全米自動車労働組合(UAW)や、ビッグスリー経営陣の一部は、表向きは保護主義を歓迎するかもしれない。しかし、その裏では、自社のグローバルなサプライチェーンを守るため、まさにその関税の対象となっている部品の適用除外を求める強力なロビー活動を展開せざるを得ない。この自己矛盾は、産業界としての統一した対応を困難にし、政策の先行き不透明感を増大させる。この政策が、グローバル化以前の、国境で完結した産業モデルを前提としていることの証左でもある。
さらに長期的な視点に立てば、この政策は米国自動車産業の国際競争力を削ぐという、意図せざる結果を招きかねない。関税という壁に守られた国内企業は、厳しい国際競争から隔離され、技術革新や効率化へのインセンティブが低下する。その一方で、米国市場から締め出された日本や欧州のメーカーは、他の市場(アジア、欧州)での生き残りをかけて、より一層の技術開発とコスト削減に邁進するだろう。加えて、トランプ政権がEV補助金を撤廃するなどの反EV政策を推し進めれば、世界の電動化の流れから米国市場だけが取り残されるリスクもある。10年後、米国は保護主義の壁の内側で、高コストで燃費の悪い、時代遅れの自動車産業を抱え、世界の技術トレンドから孤立しているという事態も十分に考えられる。
第4章:戦略的展望とシナリオ分析
これまでの分析を踏まえ、本章では日本と米国の政府および企業が取りうる戦略的対応と、今後の展開を左右する不確定要素について考察し、将来のシナリオを展望する。
4.1 日本の対応戦略
未曾有の危機に直面する日本は、外交、産業政策、企業戦略のすべてを総動員して対応にあたることになる。
- 外交交渉と報復措置のジレンマ: 日本政府は、2019年の日米共同声明などを根拠に、関税の適用除外を求める粘り強い外交交渉を展開するだろう。しかし、トランプ大統領は例外措置に興味はないと公言しており、交渉は極めて難航することが予想される。報復関税という選択肢もあるが、日本は歴史的に米国に対する報復措置を講じたことがなく、さらなる関係悪化を避けるため、今回もその選択肢は取らない可能性が高い。
- 対米輸出自主規制(VER)の再来: 最も現実的な落としどころとして浮上するのが、1980年代の日米自動車摩擦の際に導入された対米輸出自主規制(VER: Voluntary Export Restraints)の現代版である。日本側が輸出台数に上限を設けることを「自主的」に申し出ることで、トランプ政権に政治的な勝利を与えつつ、全面的な関税発動という最悪の事態を回避するシナリオだ。企業にとっては、関税よりは予測可能性が高いという利点がある。
- 米国での現地生産加速: 企業レベルでの最も直接的な対応は、関税を回避するための米国での生産移転(オンショアリング)である。すでに北米現地生産比率が99%に達するホンダは比較的影響が軽微だが、比率の低いトヨタやマツダなどは、新たな米国工場の建設や既存工場の拡張といった大規模な投資判断を迫られる。これは数年と数十億ドルを要する巨大プロジェクトであり、米国内の高い人件費や、4年後の政権交代による政策変更リスクを抱えながらの、困難な決断となる。
- サプライチェーンの再構築: 完成車のみならず、エンジンやトランスミッションといった基幹部品にも25%の関税が課されることは、事態をさらに複雑化させる。これは、サプライチェーン全体の再構築を意味する。企業は、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)の厳格な原産地規則をクリアするため、部品の北米域内での調達比率(ローカルコンテンツ)を一層引き上げる必要に迫られるだろう。
4.2 不確定要素:USMCAとEV政策の動向
関税の影響を占う上で、二つの大きな不確定要素が存在する。
- USMCAという「武器」: USMCAにおける自動車の原産地規則(域内原産割合75%以上、特定部品の域内調達義務など)は、米国にとって強力な貿易政策ツールである。トランプ政権は、2026年に予定されているUSMCAの見直し協議の場で、この規則をさらに厳格化させ、日本など域外国からの部品調達をより困難にしようとする可能性がある。これは25%の関税に加えて、日本企業への二重の圧力となる。
- EV政策の衝突: トランプ政権は、インフレ削減法(IRA)に盛り込まれたEV購入補助金の撤廃など、バイデン政権のEV推進策を覆す可能性が高い。これは、ハイブリッド車(HV)を得意とする日本メーカー(特にトヨタ)にとっては短期的に有利に働く可能性がある。しかし、一方でトランプ政権は中国製EVに対して100%という極めて高い関税を課しており、これは米国のEV産業を保護する目的である。ガソリン車を優遇しつつEV産業も保護するという、一見矛盾した政策の方向性は、自動車メーカーの長期的な投資戦略に大きな不確実性をもたらす。
4.3 結論と提言
これらの分析を総合すると、最も確からしいシナリオは、日米両政府による交渉の結果、日本が輸出台数の自主規制を受け入れ、その見返りとして25%関税の全面的な発動が凍結または部分的に緩和されるというものである。同時に、日本の自動車メーカーは、ラストベルト地帯への工場新設など、米国の世論を意識した大規模な対米投資を発表することで、政治的な解決を図ろうとするだろう。
この未来予測に基づき、以下の提言を行う。
日本の企業への提言
- 徹底的なサプライチェーンの多様化: 米国一国への依存リスクを低減するため、生産・調達網の多様化を急ぐべきである。米国への生産移転だけでなく、ASEANやインドなど、他の成長市場における生産・供給能力を複層的に構築し、地政学的リスクに対する強靭性を高めることが不可欠である。
- シナリオベースの投資計画: 今後の設備投資や研究開発計画は、「関税が4年間継続」「次期政権で撤廃」「USMCAがさらに厳格化」といった複数の政治シナリオを想定し、それぞれに対する耐性を検証すべきである。生産ラインの柔軟性やモジュール化が、不確実性の時代を乗り切る鍵となる。
- 米国内での政治的プレゼンス強化: 連邦政府レベルだけでなく、州政府や議会、地域社会に対するロビー活動を強化すべきである。日本企業がいかに多くの米国民の雇用を支え、地域経済に貢献しているかを、データに基づき具体的に訴え続けることが重要となる。
日本の政策決定者への提言
- 先を見越した通商外交: 関税が発動されてから対応するのではなく、政権移行期から次期政権と緊密な対話を開始し、破滅的な関税戦争を回避するための枠組みを構築すべきである。1980年代のVERを教訓とし、予測可能性の高い着地点を模索する、現実的な交渉戦略が求められる。
- 国内サプライチェーンへの支援策: 対米輸出の減少が避けられない場合、国内の特に中小部品メーカーが受ける打撃を緩和するための、資金繰り支援、事業転換支援、雇用調整助成金といったセーフティネットを予め準備しておく必要がある。
- 貿易相手国の多角化の加速: 国家戦略として、米国への戦略的依存度を中長期的に低減させる必要がある。環太平洋パートナーシップ(TPP)の拡大や、EU、インド、ASEAN諸国との経済連携協定(EPA)をさらに深化させ、日本の輸出市場のポートフォリオを再構築することが急務である。
この関税問題が浮き彫りにするのは、日本企業にとってのリスクの本質が、もはや為替や景気といった従来の市場リスクから、一人の指導者の判断で覆る政治リスクへと大きくシフトしたという事実である。企業の意思決定は、経済合理性だけでなく、地政学的なリスク管理という新たな変数を最優先に考慮せざるを得なくなる。
最終的に、この関税と米国の反EV政策が組み合わさることで、世界の自動車市場が二つに分断される未来が訪れるかもしれない。一方は、関税の壁に守られた米国市場で、ガソリン車とハイブリッド車が延命する。もう一方は、欧州とアジアを中心に、電動化がさらに加速する市場である。グローバル企業であるトヨタやフォルクスワーゲンは、この二つの全く異なる市場に対し、並行して異なる製品開発、サプライチェーン、マーケティング戦略を展開する必要に迫られる。これは、資本の非効率な重複投資を強いるものであり、世界全体の自動車産業の技術革新のペースを鈍化させる、大きな足枷となるだろう。
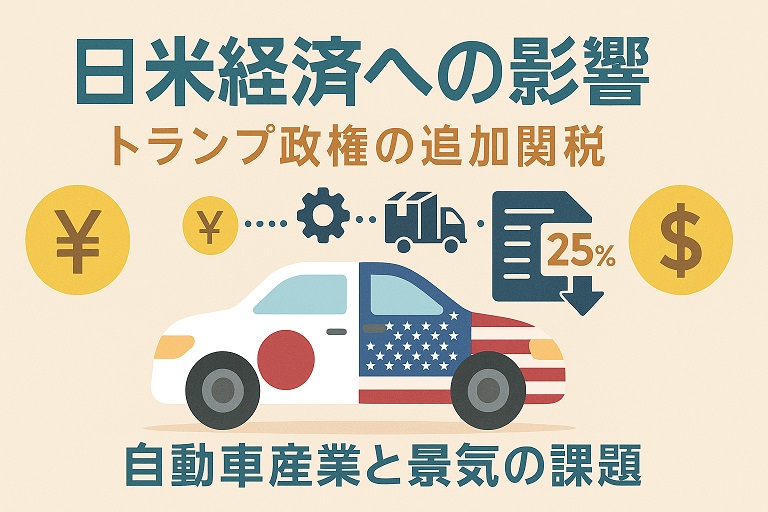


コメント