デジタル化、オートメーション、AIなどの技術革新が進む現代において、かつてのホワイトカラーの役割や働き方が急激に変化し、場合によっては消滅していく現実に対して、私たちがどのように働き方を再設計し、未来に適応すべきかを検討するものです。従来の固定的な組織や働き方の枠組みが崩れ、柔軟で自律的な働き方が求められる時代に、個人も企業もどのようなスキルやマインドセットを構築すべきか、実例やデータを交えて論じています。
ホワイトカラー職が消滅する理由
2040年には1100万人の労働力不足と同時に、ホワイトカラーの人余りが起こると予測されています。
- AIの進化により、オフィスで行われているデスクワークの8割が消滅する可能性があると著者は指摘しています。具体的には、事務、弁護士、税理士、会計、デザイン、中間管理職、コンサルティングなどの仕事です。三菱総合研究所の試算では、2035年の段階でホワイトカラー事務職が180万人余るとされています
- 一方、警察官、自衛官、介護、医療、農業、水産業、バス運転手、運搬・輸送、飲食などのエッセンシャルワーカーは深刻な人手不足に陥ります。これらの仕事はAIで代替することが難しい側面があります。三菱総合研究所の試算では、2035年の段階で専門技術職や運搬などの仕事が270万人以上の人手不足になるとされています
- 意思決定のアルゴリズム化でマーケティング戦略や人事評価さえAIが最適解を提示する時代
- コスト削減圧力で企業が人件費削減のため、人間より低コストで高精度なテクノロジーを優先
消滅リスクが高い職種の特徴
ルーティンワーク依存でマニュアル化可能な業務は10年以内に90%が代替可能
- 中間管理職の脆弱性で報告書作成や進捗管理ツールのAI化で存在意義が問われる
- 専門職の再定義で弁護士の契約書チェック、税理士の申告業務などもAI支援ツールに置換
東京から地方に目を向けることが推奨
地方では人口減少により人手不足が深刻であり、東京よりも有効求人倍率が高い地域もあります。東京は生活費が高く、地方の方が貯金や結婚、育児がしやすい可能性があります。地方の企業はAI導入によって生産性を向上させ、魅力的な雇用を生み出す必要があります。
生き残るために必要な「3つの適応力」
人間固有の価値創造
- 共感力で顧客の潜在ニーズを汲み取る「情緒的洞察」
- 複雑な調整力で利害関係が錯綜するプロジェクトの調整役としての役割
- 倫理的判断でAIが苦手な「グレーゾーン」での意思決定
テクノロジーリテラシー
- AI活用スキルでプロンプトエンジニアリングやデータ可視化ツールの操作能力
- デジタルツイン思考で現実課題を仮想空間でシミュレーションする発想力
キャリア流動性
- ポートフォリオ型キャリアで複数のスキルを掛け合わせた「ハイブリッド人材」化
- プロジェクトベース労働で企業に依存せず、案件単位で価値を提供する働き方
企業と社会が取り組むべき変革
- リカレント教育の義務化で国と企業が連携した「学び直し制度」の整備
- ジョブ型雇用への移行で職務内容を明確化し、成果ベースの評価体系を構築
- ベーシックインカム実験でAI失業者へのセーフティネットとしての検討必要性
未来の働き方の具体像
- メタバースオフィスで地理的制約を超えた「デジタルネイティブ職場」の普及
- AIパートナーシップで人間が戦略を立案し、AIが実行する「協働モデル」の一般化
- 社会的意義の可視化で利益追求だけでなく「社会課題解決」が企業価値の基準に
取るべき行動
ホワイトカラー消滅は悲観すべき事態ではなく、人間が『人間らしい働き方』を取り戻す契機である。AIに代替されない価値とは、機械的な効率性ではなく、矛盾や不確実性を包含する『人間性の深化』にこそ存在する。
本書の構成
序章 労働力消滅、ふたたび
第1章 グローバル企業は劇的に変わらざるを得ない
第2章 ローカル経済で確実に進む「人手不足クライシス」
第3章 エッセンシャルワーカーを「アドバンスト」にする
第4章 悩めるホワイトカラーとその予備軍への処方箋
第5章 日本再生への20の提言
著者について
経営コンサルタント。IGPIグループ会長。日本共創プラットフォーム代表取締役社長。1960年生まれ。東京大学法学部卒。在学中に司法試験合格。スタンフォード大学でMBA取得。2003年、産業再生機構設立時に参画しCOOに就任。解散後、2007年、経営共創基盤(IGPI)を設立し代表取締役CEO就任。2020年10月よりIGPIグループ会長。2020年、日本共創プラットフォーム(JPiX)を設立し代表取締役社長就任。パナソニックホールディングス社外取締役、メルカリ社外取締役。
書籍情報
- 出版社 : NHK出版 (2024/10/10)
- 発売日 : 2024/10/10
- 言語 : 日本語
- 新書 : 304ページ
- ISBN-10 : 4140887281
- ISBN-13 : 978-4140887288
- 寸法 : 11 x 1.4 x 17.2 cm
レビュー
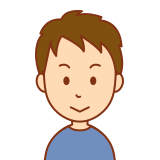
ローカルシフトが日本を救う。新時代の働き方が見えてくる
日本社会が静かに転換点を迎えている――その象徴が「ホワイトカラー消滅」という過激な表現です。本書が提起するのは、単なる“リストラ”や“大企業崩壊”のような話ではなく、デジタル革命と人口構造の変化によってオフィスワークの常識が根底から書き換えられている点にあります。しかも、かつて日本経済を支えてきた工業大量生産モデルの終焉と、「ローカル産業の人材不足」というギャップが同時進行しているからこそ、激変はより深刻になるというのです。
◎「人余り」と「人手不足」の同時進行
人口減少や高齢化によって、地域社会はとんでもない人手不足に陥っています。バスやタクシーなど交通機関の維持、水道管や道路インフラのメンテナンス、介護や医療の現場、農業・水産業、飲食・観光業など、実際にローカルで支えているのは現場ワーカーです。ここでは一人が何役も担わなければならないほど逼迫した状況にある。一方で、都市部の大企業やグローバル企業に勤めるホワイトカラーは、AIやDXにより事務や管理の多くが自動化され、さらには国際競争の激化で雇用が圧縮され続ける。人が余ってしまうわけです。こうしたねじれにより、「雇用構造」そのものが大きく揺れ動いている現実が伝わってきます。
◎グローバル×ローカルの構造変化
本書の魅力は、ただ「都市部から地方へ行こう」と単純な解を提示するのではなく、産業の構造変化と人材移動、国際競争とローカル保護といった複雑な要素をきちんと整理している点です。たとえば、本書が強調する「付加価値労働生産性」というキーワードは、単に生産コストを下げるという発想ではなく、高賃金で働く仕組みをどうつくるか、そのためにITやAIをどう活用し、サービスや商品を高付加価値化するかにかかっています。そこに「ローカルな仕事でも十分に稼げる可能性」があることを示してくれるのです。
しかも、読んでいくと、グローバル企業でキャリアを積んできた人材が地域の中堅・中小企業で実力を開花させる事例や、観光業や農業でもDXを導入して劇的に生産性を上げたケースなどが散りばめられており、「自分にもできるかもしれない」という希望を感じられます。これこそが、本書の隠れたエッセンス。現状にしがみつくだけでは未来は開けない、かといって唐突に転職すればいいというものでもない。重要なのは、いかに自分自身を“リスキリング”して、時代の変化に合わせた働き方のアップデートをするか――そこに焦点が当てられています。
◎「漫然とホワイトカラー」の危うさ
本書が繰り返し指摘するのは、「漫然とオフィスワークに身を置いている」人々の行き場が次第に狭まるという事実です。言われた仕事をこなし、資料をまとめ、会議を設定する――こうした日常のタスクこそ、DXやAIにとって一番代替しやすい領域。さらに、古い大企業の中間管理職は立場こそ安定していそうですが、実は組織構造が変わるともっとも行き場を失いやすい。現に有名企業で中高年の早期退職やリストラが常態化しているのを見れば分かるように、現場に近いか、経営を動かせるか、それとも専門性を磨くか、何らかの武器がないと厳しいのです。
しかし著者は、ただ危機感をあおるだけではありません。ローカル経済圏のサービス業やインフラ産業を「低賃金で苦労する場所」と見なすのではなく、ITやマーケティング、ブランディングを活用して効率化・高付加価値化すれば、むしろ給料も上がり、やりがいも大きい産業に変えられると強調します。かつての「農業=きついわりに稼げない」というイメージを覆す成功事例、介護や医療におけるDXの活用などを読むと、実例があるからこそ説得力を伴って胸に響いてくるのです。
◎シビアな現実だからこそ「希望」はある
読み進めるうちに、本書は単なる企業論や労働論にとどまらず、日本社会が衰退を避けつつ豊かさを持続するにはどうすればいいのか、という大局的な問題に迫っているのが分かります。少子化・高齢化の加速と、都市の空洞化、ローカルの人手不足。さらに世界的なAI革命の波が一気に押し寄せる中、私たち一人ひとりが今の仕事にしがみつくより、学び直しや新しい領域へのチャレンジをしたほうが得策ではないか。そういう“未来志向”の視点を明確に提案している点は、とても刺激的です。
特に説得力があるのは、「学び直し」に対して大人が二の足を踏む心理に対するコメントでしょう。40代や50代になってからプログラミングを学び直すのは難しい、英語をもう一度真剣にやるのはハードルが高い、と思ってしまいがち。しかし、それをやらなければアナログ仕事が激減する将来に行き場がなくなるかもしれない。そのかわり、“AIが苦手とする現場技能”や“人間ならではのコミュニケーション領域”にフォーカスすれば、大きく飛躍できる可能性もあると説くのです。
◎読後感と実践的アクション
本書を読み終えると、日本全体が「みんなで頑張ればなんとかなる」段階にはなく、構造的な変化の波が容赦なく押し寄せているのだと痛感します。しかし同時に、だからこそ個々の生き方を変える余地が大きい。ローカルや現場に目を向ければ人材不足というチャンスがあり、デジタル化で世界との距離が縮まり、付加価値を創出すれば十分に稼げる――どこにどう踏み出すかで人生が変わる、という期待が湧き上がるのです。
「ホワイトカラー消滅」という衝撃的なフレーズとは裏腹に、本書の余韻は明るい。日本を支えてきた産業のありようが時代遅れになってしまったからといって、次の産業が生まれないわけではありません。たとえば観光業や食品、介護、公共インフラなどの領域を、DXと組み合わせてイノベーションすれば、これまで想像もしなかった収益モデルが生まれる可能性がある。大企業の歯車に過ぎなかった人が、地域の中小企業で経営幹部として目覚ましい活躍をするかもしれないのです。
本書を読むと、働き方やキャリアに不安を抱える人こそ「待ったなし」で新しい世界を見据えるべきだと背中を押されるはず。明日すぐに大企業を辞めろという意味ではなく、いかに学び、いかに新しい価値を創り出すか、その心構えを鍛える“ビジョン”を与えてくれる一冊だと感じます。
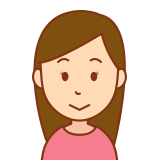
身の振り方を考えさせられる
ポンコツサラリーマンとしては、都市部のホワイトカラー過剰と地方の現場人材の人手不足は耳の痛い話です。ホワイトカラー→現場人材の移行は、日本社会全体でみたらその必要性は理解できるものの、待遇や職場環境・風土(田舎のムラ社会から若い人、女性が離れたがるのは当然ですよ…)が違い過ぎて、自分が移りたいかというとNoです。現場人材の働く環境・待遇改善は急務だと思います。
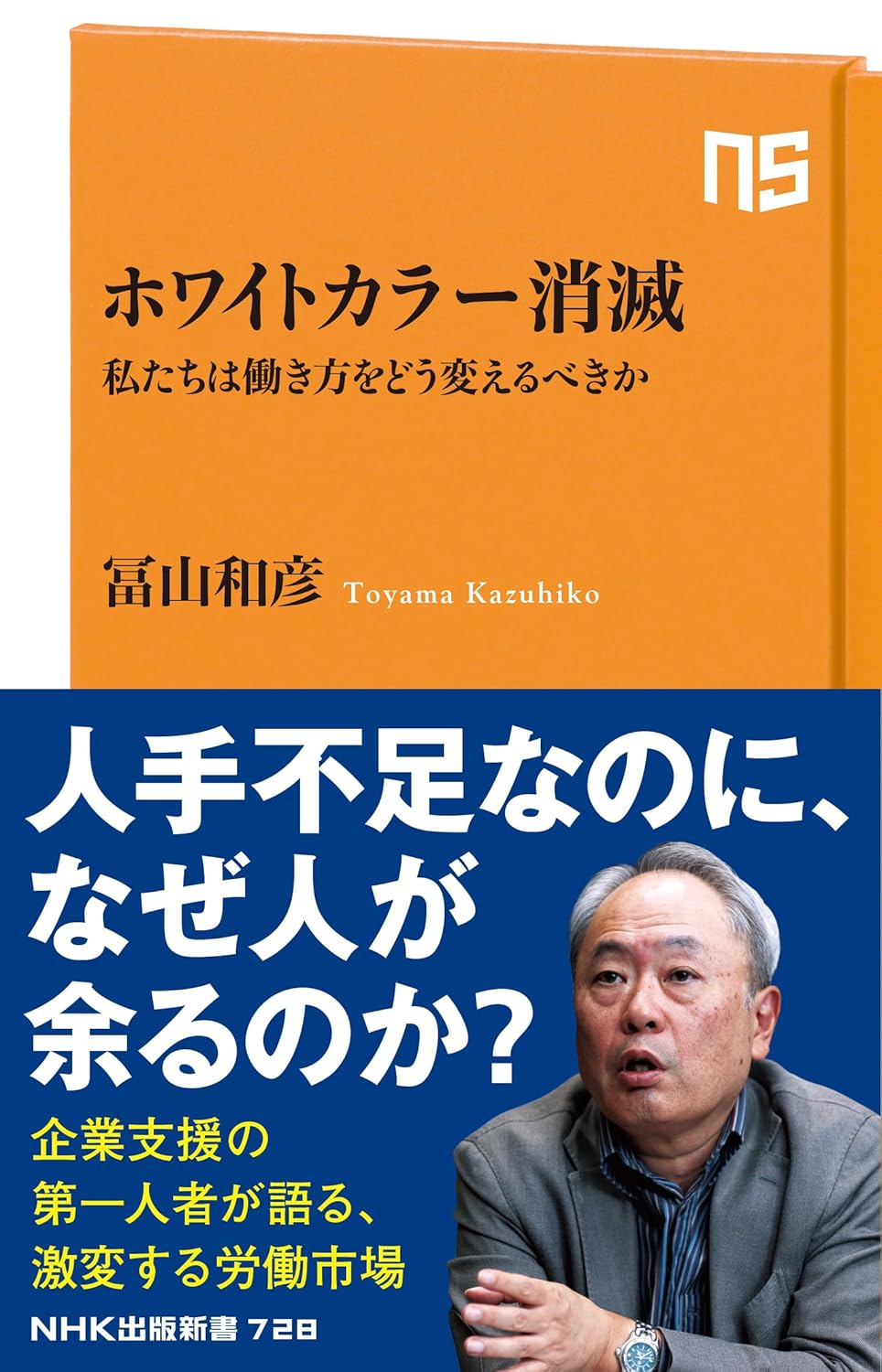


コメント