鉄分は、人体にとって必須のミネラルであり、主に赤血球中のヘモグロビンや筋肉中のミオグロビンの構成成分として働いています。これらのタンパク質は、酸素の運搬や貯蔵に欠かせず、エネルギー産生や細胞の代謝活動、さらにはDNA合成、免疫機能の調整にも大きく寄与しています。
鉄分の役割
- 酸素運搬
ヘモグロビンにより肺から全身に酸素が運ばれ、組織のエネルギー代謝を支える - 酸素貯蔵
ミオグロビンは筋肉内で酸素を貯蔵し、運動時などに速やかに酸素を供給する - エネルギー生成
ミトコンドリアでのエネルギー産生過程において、鉄は重要な酵素反応の補因子として働く - 免疫機能
一部の免疫細胞にも鉄が必要で、感染症と戦うための細胞機能の維持に関与する - 神経伝達物質の合成
ドーパミンやセロトニンの生成をサポート
鉄分が不足すると?
鉄分不足、つまり鉄欠乏状態になると、以下のような影響が現れます。
- 鉄欠乏性貧血はヘモグロビン濃度の低下により、体内への酸素供給が不十分になり、疲労感、息切れ、動悸、爪の変形(スプーン状爪)、めまいなどの症状が発生します
- 免疫低下する鉄不足は免疫細胞の働きを低下させ、感染症にかかりやすくなります
- 集中力の低下・認知機能障害で脳への酸素供給不足により、思考力や集中力の低下、記憶力の障害が生じることがあります
- 氷食症で氷を無性に食べたくなる異食症がでます
鉄分が女性に重要な理由
女性は月経による鉄分の損失が相対的に大きく、また妊娠・出産、授乳といったライフステージにおいても鉄分需要が増加します。そのため、適切な鉄分の摂取が不足すると、鉄欠乏性貧血やそれに伴う疲労、集中力の欠如、免疫低下などが起こりやすいため、女性では特に重要視されています。
- 月経による損失
月経時に毎月約20〜30mgの鉄を失う(男性の約2倍の必要量) - 妊娠・授乳期の需要増
胎児の成長や母乳分泌で鉄需要が増加(妊娠後期は1日27mg必要) - 貧血リスクの高さ
女性の約40%が潜在的な鉄欠乏状態(フェリチン低値)
フェリチンってなに?
フェリチンは、鉄分を細胞内に貯蔵する役割を持つタンパク質です。血中のフェリチン濃度を測定することで、体内にどれくらいの鉄が蓄えられているかを知ることができ、鉄欠乏や鉄過剰状態の診断に有用なバイオマーカーとされています。
- 体内の貯蔵鉄を反映するタンパク質で血液検査で測定され、鉄欠乏の早期指標となる
- 基準値は男性30〜300ng/mL、女性10〜150ng/mL
- 低フェリチンは30ng/mL未満で鉄欠乏状態、10ng/mL未満で貧血の可能性が高い
低フェリチン状態と鬱の関係
フェリチンは体内の「貯蔵鉄」を反映するタンパク質で、鉄欠乏の早期指標です。フェリチン値が低下(鉄分枯渇)すると、脳の機能や神経伝達物質の合成に深刻な影響を及ぼし、うつ症状を引き起こすリスクが高まります。
フェリチンの鉄分枯渇は、「隠れうつ」の原因になり得ます。特に女性や食事制限のある人は要注意です。うつ症状と鉄欠乏は表裏一体の関係にあるため、心療内科だけでなく内科的なアプローチも併用することが重要です。
低フェリチンが鬱を引き起こすメカニズム
(1) 神経伝達物質の合成障害
- セロトニン・ドーパミン・ノルアドレナリンの合成には鉄が必要
- 鉄は酵素「トリプトファンヒドロキシラーゼ」の補因子として、セロトニン合成を促進
- ドーパミン合成には「チロシンヒドロキシラーゼ」が鉄を必要
- 鉄不足→ 神経伝達物質の産生低下 → 意欲喪失・気分の落ち込み・不安感が生じる
(2) 脳のエネルギー不足
- 鉄はミトコンドリアでのATP(エネルギー)産生に必須
- 鉄欠乏により脳細胞のエネルギー代謝が低下 → 疲労感・集中力低下・無気力が持続する
(3) 脳内炎症の促進
- 鉄不足は脳の酸化ストレスを増加させ、炎症性サイトカイン(IL-6など)の産生を促す
- 慢性炎症は神経細胞の損傷やうつ状態と関連する
フェリチン値とうつリスクの具体的データ
- フェリチン基準値
- 男性30〜300ng/mL、女性10〜150ng/mL(※施設により異なる)
- <30ng/mLで鉄欠乏、<10ng/mLで鉄欠乏性貧血の可能性
- うつリスクとの関連
- フェリチン値が50ng/mL未満の人は、うつ症状を発症するリスクが2倍以上上昇(2021年メタ分析)
- フェリチン値が低い女性では、疲労感や抑うつスコアが有意に高い(米国精神医学会報告)
鉄分補給によるうつ症状の改善例
フェリチン低値のうつ患者に鉄剤を投与した研究
- 6週間の鉄補給で、抑うつスコアが40%改善(Journal of Psychiatric Research, 2017)
- 特に「疲労感」「集中力低下」の改善が顕著
- 非貧血性鉄欠乏(フェリチン<50ng/mL)でも、鉄補給で気分障害が軽減されるケースが報告
鉄分枯渇とうつの「見逃されやすい関係」
- 隠れ鉄欠乏
- フェリチン低値でもヘモグロビンは正常な場合が多く、貧血と診断されないため、うつ症状の原因が鉄不足と気づかれません
- 特に月経のある女性やヴィーガンはリスクが高い
- 誤診の危険性
- うつ病と診断され抗うつ薬が処方されても、根本原因が鉄欠乏の場合、効果が限定的
対処法とアドバイス
- フェリチン検査の実施
- うつ症状がある場合は、血液検査でフェリチン値を必ず確認
- 理想はフェリチン100ng/mL以上を目指す(機能医学的な観点)
- 鉄分摂取の最適化:
- ヘム鉄(赤身肉・レバー)を優先
- 非ヘム鉄(ひじき・小松菜)はビタミンCと一緒に摂取し吸収率UP
- サプリメント使用時は医師の指導のもと、過剰摂取(※上限40〜50mg/日)に注意
- 生活習慣の改善:
- 月経過多の場合は婦人科受診
- コーヒー・紅茶のタンニンは鉄吸収を阻害するため、食後30分空けて摂取
鉄分の推奨摂取量
日本人男性と女性の年齢別の鉄分の一日推奨摂取量です。
| 年齢 | 男性 (mg/日) | 女性 (mg/日) |
|---|---|---|
| 0〜5ヶ月 | 0.5 | 0.5 |
| 6〜11ヶ月 | 5.0 | 4.5 |
| 1〜2歳 | 4.0 | 4.5 |
| 3〜5歳 | 5.5 | 5.5 |
| 6〜7歳 | 6.5 | 6.5 |
| 8〜9歳 | 8.5 | 8.0 |
| 10〜11歳 | 10.0 | 9.5 |
| 12〜14歳 | 11.0 | 10.0 |
| 15〜17歳 | 9.5 | 8.5 |
| 18〜29歳 | 7.0 | 6.0 |
| 30〜49歳 | 7.5 | 6.5 |
| 50〜69歳 | 7.5 | 6.5 |
| 70歳以上 | 7.0 | 6.0 |
| 妊婦 (初期) | – | +2.0 |
| 妊婦 (中期・末期) | – | +9.5 |
| 授乳婦 | – | +2.5 |
鉄分の含有量が多い食品
鉄分の含有量が多い順に並べた表です。
レバーは鉄分が多そうなイメージがありますが、あおのりの含有量は豚レバーの約6倍あります。
| 品名 | 含有量 (mg/100g) | 区分 |
|---|---|---|
| あおのり (乾) | 74.8 | 野菜 |
| ひじき (乾) | 55.0 | 野菜 |
| きくらげ (乾) | 35.2 | 野菜 |
| 豚レバー | 13.0 | 肉 |
| パセリ | 7.5 | 野菜 |
| 鶏レバー | 9.0 | 肉 |
| 牛レバー | 4.0 | 肉 |
| 納豆 | 3.3 | 野菜 |
| 小松菜 | 2.8 | 野菜 |
| ほうれん草 | 2.7 | 野菜 |
| あゆ (焼) | 5.5 | 魚 |
| しじみ | 5.3 | 魚 |
| うなぎの肝 | 4.6 | 魚 |
| いわし (丸干) | 4.4 | 魚 |
| かつお | 1.9 | 魚 |
ヘム鉄と非ヘム鉄の比較
鉄分含有量が最も多いあおのり100gには74.8mgの鉄分が含まれています。仮に吸収率を一番高い5%とすると、実際に体内に吸収される鉄分は 74.8mg × 0.05 = 3.74mg となります。
このように、あおのり100gからの鉄分摂取量が74.8mgであっても、実際に体内に吸収されるのは約3.74mgです。
| 特徴 | ヘム鉄 | 非ヘム鉄 |
|---|---|---|
| 含有物 | 動物性 | 植物性 |
| 吸収率 | 高い 15〜25% | 低い 2〜5% |
| 含有食品 | 肉、魚 | 野菜、果物 |
| 胃腸への影響 | 少ない | 多い |
| 吸収に影響する要因 | 影響されにくい | 食べ合わせに影響される |
| 特徴 | 鉄イオンが保護されている | 鉄イオンがむき出し |
| デメリット | ・価格が高い ・ベジタリアン不向き | ・吸収率が低い ・胃腸障害のリスク |
| 適している人 | ・吸収力が弱い人 ・胃腸が敏感な人 | ・コストを抑えたい人 ・軽度の不足 |
ヘム鉄は肉や魚に多く含まれ、吸収率が高く、胃腸への負担が少ないのが特徴です。非ヘム鉄は野菜や果物に含まれ、吸収率が低く、食べ合わせによって吸収率が変わることがあります。
キレート鉄サプリとは?
キレート鉄サプリは、鉄イオンがアミノ酸や有機酸などのキレート剤と結合しているサプリメントです。この結合状態により、鉄の吸収が促進され、胃腸への刺激や副作用が軽減されることが期待されています。
総じて、キレート鉄サプリは鉄分の効率的な吸収を促進し、胃腸への負担を軽減するという点では大きなメリットがあります。一方で、コストの高さや過剰摂取のリスク、製品の品質管理の必要性などのデメリットが存在します。自分自身の健康状態や摂取する食事内容、既往症などを考慮し、医師や栄養士と相談の上で摂取することが望まれます。
| 特徴 | ヘム鉄 | 非ヘム鉄 | キレート鉄 |
|---|---|---|---|
| 含有物 | 動物性 | 植物性 | 加工鉄 |
| 吸収率 | 高い 15〜25% | 低い 2〜5% | 非常に高い 20~40% |
| 含有食品 | 肉、魚 | 野菜、果物 | サプリメント |
| 胃腸への影響 | 少ない | 多い | 少ない |
| 吸収に影響する要因 | 影響されにくい | 食べ合わせに影響される | 影響されにくい |
| 特徴 | 鉄イオンが保護されている | 鉄イオンがむき出し | アミノ酸やクエン酸でキレート加工 |
| デメリット | ・価格が高い ・ベジタリアン不向き | ・吸収率が低い ・胃腸障害のリスク | ・価格が高め ・製品によって差がある |
| 適している人 | ・吸収力が弱い人 ・胃腸が敏感な人 | ・コストを抑えたい人 ・軽度の不足 | ・吸収効率を重視する人 ・継続派 |
キレート鉄はサプリメントに含まれ、吸収率が非常に高く、胃腸への負担が少ないのが特徴です。
実際に厚生労働省が推奨している1日の鉄分量を摂取するのは難しく、やはりサプリを栄養補助食として摂取するのはとても有効であるか考えられます。
メリット
キレート鉄は、通常の鉄塩(硫酸鉄など)に比べ、胃腸内の環境や他の食事成分(例えばフィチン酸やタンニン)による吸収阻害が少なく、より効率的に鉄が吸収されやすいとされています。
- 胃腸への負担が少ない
鉄がキレートされることで、直接的に胃腸粘膜に刺激を与えにくく、便秘や胃痛、吐き気といった副作用が比較的軽減される場合が多いです。 - 安定した鉄供給
キレート鉄は、体内で効率的に利用されるため、鉄欠乏性貧血の改善や予防に効果的とされ、定期的な補給が必要な方に適しています。 - 他の栄養素との相互作用の軽減
キレート状態にあるため、鉄と他の食材中の要因との結合による吸収障害が少なく、外部要因に左右されにくいというメリットがあります。
デメリット
- コストが高い
キレート鉄サプリは、製造工程や使用するキレート剤の品質、技術的要因から価格が高くなる傾向にあります。長期的に摂取する場合、経済的負担が増す可能性があります。 - 過剰摂取のリスク
吸収率が高い分、過剰に摂取すると鉄の蓄積(鉄過剰症)につながる可能性があります。特に遺伝的に鉄の代謝に問題がある場合や、鉄補給の管理が不十分な場合には注意が必要です。 - 個人差がある
キレート鉄の効果は個人の胃腸機能や代謝状態によって異なるため、必ずしも全ての人に同じ効果が得られるわけではありません。また、副作用の有無も個人差が見られます。 - 品質のばらつき
キレート鉄製品はメーカーや使用されるキレート剤によって、吸収効率や安全性に差が出る可能性があります。そのため、製品選びや信頼できるメーカーの選定が重要です。
なぜキレート鉄は吸収されやすいのか?
キレート鉄の吸収率がヘム鉄や非ヘム鉄よりも高い理由は、非ヘム鉄の吸収経路(DMT1トランスポーター)よりもキレート構造のままアミノ酸トランスポーターを利用し小腸粘膜細胞に取り込まれるためです。また競合するミネラル(亜鉛、カルシウム)の影響を受けにくいです。
化学構造の違い
- キレート鉄
鉄(Fe²⁺またはFe³⁺)がアミノ酸(例:グリシン)や有機酸(例:クエン酸)と結合し、安定した「キレート構造」を形成しています。鉄が腸内での分解や他の成分との結合(例:フィチン酸、タンニン)から保護され、吸収されやすい状態を維持します。
キレート鉄もビタミンCと一緒に摂取すると、還元作用で吸収率がさらに向上します。 - ヘム鉄
ヘム鉄は小腸の「ヘムキャリア」と呼ばれる専用の経路で吸収されますが、ベジタリアン・ビーガンは摂取できません。 - 非ヘム鉄
イオン化しやすく、腸内で他の成分(食物繊維、カルシウムなど)と結合し、吸収が阻害されやすい。
吸収メカニズムの違い
- キレート鉄の吸収経路
- キレート構造のままアミノ酸トランスポーターを利用し小腸粘膜細胞に取り込まれます。
- 非ヘム鉄の吸収経路(DMT1トランスポーター)よりも効率的で、競合するミネラル(亜鉛、カルシウム)の影響を受けにくい。
- 非ヘム鉄の吸収経路
- 胃酸で「Fe²⁺」に還元された後、小腸の「DMT1トランスポーター」で吸収されます。
- この経路は他のミネラルや成分(例:コーヒー・紅茶のタンニン)と競合し、吸収率が低下します。
- ヘム鉄の吸収経路
- ヘム鉄は構造が複雑なため、吸収には「ヘムキャリア」という特殊な経路が必要です。
- 吸収率は非ヘム鉄より高い(約15-35%)ですが、キレート鉄と比べると吸収効率に差があります。

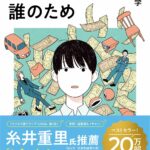

コメント